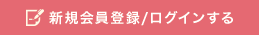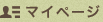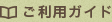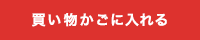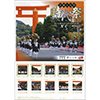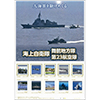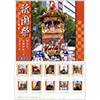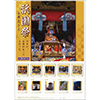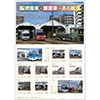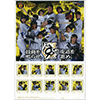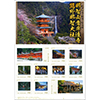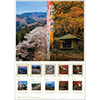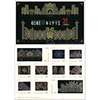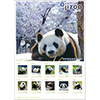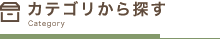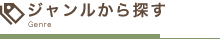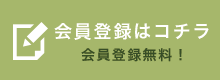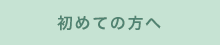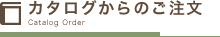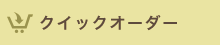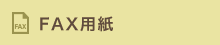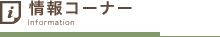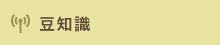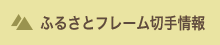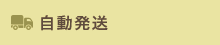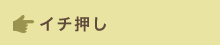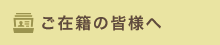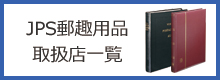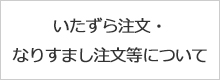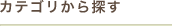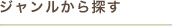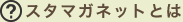近畿支社
近畿支社が発行した大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀、和歌山の2府4県のふるさとフレーム切手です。

609054
近畿
2025年阪神タイガースは球団創設90周年という節目の年を迎えました。さらに藤川球児監督のもと、選手・スタッフ・ファンが一丸となり、セ・パ両リーグ史上最速優勝という偉業を達成!
シート地には藤川球児監督胴上げの歓喜の瞬間がデザインされています。
シート地には藤川球児監督胴上げの歓喜の瞬間がデザインされています。

609008
京都
時代祭は、京都市の平安神宮の祭りで、葵祭や祇園祭に比べると歴史は浅いものの、京都三大祭りの一つです。
●行在所祭
●維新勤王隊列
●維新志士列
●徳川城使上洛列
●江戸時代婦人列
●豊公参朝列
●室町洛中風俗列
●楠公上洛列
●平安時代婦人列
●神幸列
●行在所祭
●維新勤王隊列
●維新志士列
●徳川城使上洛列
●江戸時代婦人列
●豊公参朝列
●室町洛中風俗列
●楠公上洛列
●平安時代婦人列
●神幸列
608986
京都
京都競馬場100周年を記念! 三冠馬かつ顕彰馬の11頭の雄姿が収められています。
●第4回菊花賞 セントライト、第25回菊花賞 シンザン
●第44回菊花賞 ミスターシービー
●第45回菊花賞 シンボリルドルフ
●第11回エリザベス女王杯 メジロラモーヌ
●第55回菊花賞 ナリタブライアン
●第66回菊花賞 ディープインパクト
●第72回菊花賞 オルフェーヴル
●第17回秋華賞 ジェンティルドンナ
●第23回秋華賞 アーモンドアイ
●第81回菊花賞 コントレイル
●第4回菊花賞 セントライト、第25回菊花賞 シンザン
●第44回菊花賞 ミスターシービー
●第45回菊花賞 シンボリルドルフ
●第11回エリザベス女王杯 メジロラモーヌ
●第55回菊花賞 ナリタブライアン
●第66回菊花賞 ディープインパクト
●第72回菊花賞 オルフェーヴル
●第17回秋華賞 ジェンティルドンナ
●第23回秋華賞 アーモンドアイ
●第81回菊花賞 コントレイル
608895
大阪・奈良
近畿日本鉄道(近鉄)の特急列車をモチーフとしたオリジナルフレーム切手が登場!
近鉄が特急列車をテーマに様々なイベント(博覧会)を開催していることにあわせ販売されたもので、近鉄特急や人気の観光列車が題材。
シート地や切手には、80000系「ひのとり」、50000系「しまかぜ」、23000系「伊勢志摩ライナー」、16200系「青の交響曲」、19200系「あをによし」の5車体が採用されています。
●80000系「ひのとり」
●50000系「しまかぜ」
●23000系「伊勢志摩ライナー」
●16200系「青の交響曲」
●19200系「あをによし」
近鉄が特急列車をテーマに様々なイベント(博覧会)を開催していることにあわせ販売されたもので、近鉄特急や人気の観光列車が題材。
シート地や切手には、80000系「ひのとり」、50000系「しまかぜ」、23000系「伊勢志摩ライナー」、16200系「青の交響曲」、19200系「あをによし」の5車体が採用されています。
●80000系「ひのとり」
●50000系「しまかぜ」
●23000系「伊勢志摩ライナー」
●16200系「青の交響曲」
●19200系「あをによし」
608892
京都
第23航空隊は海上自衛隊で唯一となる日本海側の航空基地で、昼夜を問わず防衛警備の任にあたっています。切手には、舞鶴地方隊の艦艇や第23航空隊の航空機の写真がデザインされており、艦艇は護衛艦「あさぎり(DD-151)」、ミサイル艇「はやぶさ(PG-824)」などの写真が収められています。
●護衛艦あさぎり・やはぎ・あがの
●降下訓練
●海軍記念館
●ミサイル艇はやぶさ・うみたか
●第23航空隊 SH-60K
●舞鶴教育隊終業式
●掃海艇あいしま
●特殊消防車放水訓練
●水中処分隊
●護衛艦ふゆづき
●護衛艦あさぎり・やはぎ・あがの
●降下訓練
●海軍記念館
●ミサイル艇はやぶさ・うみたか
●第23航空隊 SH-60K
●舞鶴教育隊終業式
●掃海艇あいしま
●特殊消防車放水訓練
●水中処分隊
●護衛艦ふゆづき
608878
京都
日本の三大祭の1つである「祇園祭」。豪華絢爛な山鉾が立ち並び、『コンチキチン♪』と鳴る鉦の音と、太鼓、笛によって奏でられる「お囃子」が響き渡ります。
この時期の京都市内は祇園祭一色となり、7月1日から始まり31日の「疫神社夏越祭」まで1ヵ月を通して祭事が行われ、特に「宵山」と「山鉾巡行」には全国からも多くの方が訪れます。
●綾傘鉾・前祭
●岩戸山・前祭
●菊水鉾・前祭
●鶏鉾・前祭
●鯉山・後祭
●船鉾・前祭
●長刀鉾・前祭
●蟷螂山・前祭
●孟宗山・前祭
●北観音山・後祭
この時期の京都市内は祇園祭一色となり、7月1日から始まり31日の「疫神社夏越祭」まで1ヵ月を通して祭事が行われ、特に「宵山」と「山鉾巡行」には全国からも多くの方が訪れます。
●綾傘鉾・前祭
●岩戸山・前祭
●菊水鉾・前祭
●鶏鉾・前祭
●鯉山・後祭
●船鉾・前祭
●長刀鉾・前祭
●蟷螂山・前祭
●孟宗山・前祭
●北観音山・後祭
608879
京都
日本の三大祭の1つである「祇園祭」。豪華絢爛な山鉾が立ち並び、『コンチキチン♪』と鳴る鉦の音と、太鼓、笛によって奏でられる「お囃子」が響き渡ります。
この時期の京都市内は祇園祭一色となり、7月1日から始まり31日の「疫神社夏越祭」まで1ヵ月を通して祭事が行われ、特に「宵山」と「山鉾巡行」には全国からも多くの方が訪れます。
お稚児さんは、神社やお寺で行われる伝統行事で、華やかな衣装を着た子どもたちが神様や仏様にお仕えする役目を果たす、欠かすことのできない存在です。
●長刀鉾・山鉾巡行×5
●長刀鉾・稚児社参
●辻廻し
●山鉾建て
●祇園祭・前祭×2
この時期の京都市内は祇園祭一色となり、7月1日から始まり31日の「疫神社夏越祭」まで1ヵ月を通して祭事が行われ、特に「宵山」と「山鉾巡行」には全国からも多くの方が訪れます。
お稚児さんは、神社やお寺で行われる伝統行事で、華やかな衣装を着た子どもたちが神様や仏様にお仕えする役目を果たす、欠かすことのできない存在です。
●長刀鉾・山鉾巡行×5
●長刀鉾・稚児社参
●辻廻し
●山鉾建て
●祇園祭・前祭×2
608847
大阪
あびこ道車庫や停留場などで路面電車と郵便車が並ぶシーンをデザインしました。
●阪堺電車と郵便車と堺柳之町局 堺柳之町郵便局前
●阪堺電車と郵便車 あびこ道車庫×4
●阪堺電車と郵便車 東粉浜駅×4
●阪堺電車と郵便車と堺柳之町局と配達員 神明町駅
●阪堺電車と郵便車と堺柳之町局 堺柳之町郵便局前
●阪堺電車と郵便車 あびこ道車庫×4
●阪堺電車と郵便車 東粉浜駅×4
●阪堺電車と郵便車と堺柳之町局と配達員 神明町駅
608827
滋賀
JR湖西線50周年記念。湖西線は、昭和49年(1974)に旧国鉄により琵琶湖西岸の旧江若鉄道に代わる基幹路線として整備され、令和6年(2024)7月20日で開通50周年を迎えました。
切手には、雪化粧した比良山系や琵琶湖など、滋賀県・湖西の四季折々の沿線風景を背に疾走する湖西線の車両の写真などが収められています。
切手には、雪化粧した比良山系や琵琶湖など、滋賀県・湖西の四季折々の沿線風景を背に疾走する湖西線の車両の写真などが収められています。
608828
近畿
シート地には、藤川監督を中心に有力選手が一堂に会した一枚絵にデザイン。切手には、藤川監督と人気選手ら10人がそれぞれの背番号とともに収められています。
●35 SAIKI
●41 MURAKAMI
●2 UMENO
●3 OHYAMA
●8 SATO
●51 NAKANO
●1 MORISHITA
●5 CHIKAMOTO
●58 MAEGAWA
●22 FUJIKAWA
●35 SAIKI
●41 MURAKAMI
●2 UMENO
●3 OHYAMA
●8 SATO
●51 NAKANO
●1 MORISHITA
●5 CHIKAMOTO
●58 MAEGAWA
●22 FUJIKAWA
608823
兵庫
垂水区が誇る史跡・五色塚古墳は、1975年に国内で初めて築造当時の姿に復元整備され、2025年で50年目を迎えました。
全長194メートルを誇る兵庫県下最大の前方後円墳で、訪れるとその雄大さと古代の技術を体感できます。
また墳頂(古墳の上)まで階段が整備されており、明石海峡大橋や淡路島を一望できる絶景スポットとして親しまれています。
全長194メートルを誇る兵庫県下最大の前方後円墳で、訪れるとその雄大さと古代の技術を体感できます。
また墳頂(古墳の上)まで階段が整備されており、明石海峡大橋や淡路島を一望できる絶景スポットとして親しまれています。
608821
京都
爽やかな初夏の京都を優雅な行列で彩る葵祭。今から約1500年前に始まったとされる賀茂御祖神社(下鴨神社)と賀茂別雷神社(上賀茂神社)の例祭です。
5月初旬からさまざまな行事(前儀)が行われ、5月15日に行われる「葵祭」のハイライト「路頭の儀」では、華やかな平安装束に身を包んだ行列がおよそ8キロの道のりをゆっくりと練り歩きます。
5月初旬からさまざまな行事(前儀)が行われ、5月15日に行われる「葵祭」のハイライト「路頭の儀」では、華やかな平安装束に身を包んだ行列がおよそ8キロの道のりをゆっくりと練り歩きます。
608788
和歌山
和歌山、三重、奈良の三県にまたがる、「紀伊山地の霊場と参詣道」。豊かな自然がもたらした「山岳霊場」と「参詣道」の歴史的環境、自然的環境、人文的環境の他に、「文化的景観」が日本で最初に評価された世界遺産で、世界でも類を見ない資産のひとつとして高く評価されています。その中の那智山青岸渡寺と熊野那智大社を中心に切手に収めました。
シート地は那智山青岸渡寺の三重塔と那智大滝。
●熊野那智大社本殿
●熊野那智大社拝殿
●三重塔と那智大滝
●飛瀧神社と那智の滝
●那智の扇祭り(大松明)
●那智の田楽
●山門
●大門坂と平安衣装
●行者堂
●那智山青岸渡寺
シート地は那智山青岸渡寺の三重塔と那智大滝。
●熊野那智大社本殿
●熊野那智大社拝殿
●三重塔と那智大滝
●飛瀧神社と那智の滝
●那智の扇祭り(大松明)
●那智の田楽
●山門
●大門坂と平安衣装
●行者堂
●那智山青岸渡寺
608784
大阪
「ミャクミャク」と「ぽすくま」が共演!
2025年4月13日から10月13日までの期間、大阪市夢洲地区で開催されている「日本国際博覧会(大阪・関西万博)」。
万博会場内の「EXPO2025 WEST郵便局」と「EXPO2025 EAST郵便局」の2カ所で限定発売されている、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品です。
※ポストカード、A3二つ折り台紙付き。
2025年4月13日から10月13日までの期間、大阪市夢洲地区で開催されている「日本国際博覧会(大阪・関西万博)」。
万博会場内の「EXPO2025 WEST郵便局」と「EXPO2025 EAST郵便局」の2カ所で限定発売されている、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品です。
※ポストカード、A3二つ折り台紙付き。
608761
奈良
吉野山は奈良県の中央部・吉野郡吉野町にある吉野川南岸から大峰山脈まで及ぶ尾根続きの山稜の総称。古くから花の名所として知られ、特に桜は有名で、日本さくら名所100選に選定されました。
秋の紅葉シーズンには、春の淡い桜色とは対照的な燃えるような赤や橙色に山全体が覆われ、見事な光景となります。
●吉野山の夕暮れ
●金峯山寺蔵王堂と桜
●滝桜
●高城山
●吉野山ロープウェイ
●東南院
●南朝妙法殿
●吉野山の雲海
●西行庵
●吉水神社
秋の紅葉シーズンには、春の淡い桜色とは対照的な燃えるような赤や橙色に山全体が覆われ、見事な光景となります。
●吉野山の夕暮れ
●金峯山寺蔵王堂と桜
●滝桜
●高城山
●吉野山ロープウェイ
●東南院
●南朝妙法殿
●吉野山の雲海
●西行庵
●吉水神社
608758
神奈川・山梨・長野・静岡・京都・大阪・兵庫・和歌山
販売価格(税込):
¥2,630
在庫:
売切れ
「全国登山鉄道‰(パーミル)会」は、2024年9月に結成15周年を迎えました。切手には、加盟7社の車両写真などを収めました。
●全国登山鉄道‰(パーミル)会のロゴマーク
●神戸電鉄(神戸電鉄 3000系)
●南海電鉄(南海電気鉄道 こうや花鉄道「天空」)
●叡山電車(叡山電鉄 900系「きらら」)
●アルピコ交通(アルピコ交通 20100形)
●大井川鐡道(大井川鐵道 ED90形)
●富士山麓電鉄(富士山麓電気鉄道 8000系「フジサン特急」)
●箱根登山電車(小田急箱根 3000形「アレグラ」)
●50‰の上り匂配標
●シート地イラスト
「全国登山鉄道‰(パーミル)会」…株式会社小田急箱根、富士山麓電気鉄道株式会社、大井川鐵道株式会社、アルピコ交通株式会社、叡山電鉄株式会社、南海電気鉄道株式会社、神戸電鉄株式会社の7社では、『観光地が沿線にあり、かつ登山鉄道としての性格を有している』という共通点から、勾配を示す単位「‰」(パーミル)になぞらえた「全国登山鉄道‰(パーミル)会」を結成し、共同での旅客誘致に努めています。
●全国登山鉄道‰(パーミル)会のロゴマーク
●神戸電鉄(神戸電鉄 3000系)
●南海電鉄(南海電気鉄道 こうや花鉄道「天空」)
●叡山電車(叡山電鉄 900系「きらら」)
●アルピコ交通(アルピコ交通 20100形)
●大井川鐡道(大井川鐵道 ED90形)
●富士山麓電鉄(富士山麓電気鉄道 8000系「フジサン特急」)
●箱根登山電車(小田急箱根 3000形「アレグラ」)
●50‰の上り匂配標
●シート地イラスト
「全国登山鉄道‰(パーミル)会」…株式会社小田急箱根、富士山麓電気鉄道株式会社、大井川鐵道株式会社、アルピコ交通株式会社、叡山電鉄株式会社、南海電気鉄道株式会社、神戸電鉄株式会社の7社では、『観光地が沿線にあり、かつ登山鉄道としての性格を有している』という共通点から、勾配を示す単位「‰」(パーミル)になぞらえた「全国登山鉄道‰(パーミル)会」を結成し、共同での旅客誘致に努めています。
608734
京都
第八管区海上保安本部・海上保安学校は、海上保安庁の教育機関として、海上保安業務に必要な知識・技能を教授し、あわせて心身の錬成を図ることを目的に、昭和26年4月に穏やかに潮香る舞鶴の地に開校しました。
●海上保安庁巡視船わかさ・米軍沿岸警備隊巡視船WAESCHE
●巡視船わかさ搭載艇
●巡視船あおい
●航空機MH914まいづる
●経ケ岬灯台
●海上保安学校入学式
●うみまる・うーみん・巡視船わかさ
●巡視船こじま
●海上保安学校
●巡視船みうら
●海上保安庁巡視船わかさ・米軍沿岸警備隊巡視船WAESCHE
●巡視船わかさ搭載艇
●巡視船あおい
●航空機MH914まいづる
●経ケ岬灯台
●海上保安学校入学式
●うみまる・うーみん・巡視船わかさ
●巡視船こじま
●海上保安学校
●巡視船みうら
608732
和歌山
ジャイアントパンダ日中「共同繁殖研究30周年」を記念!
和歌山県白浜町のテーマパーク・アドベンチャーワールドのパンダファミリー全20頭の写真入りの特別なフレーム切手をセットにしました。
【A】
●永明ーEIMEI
●蓉浜ーYOUHIN
●梅梅ーMEIMEI
●雄浜ーYUHIN
●隆浜ーRYUHIN
●秋浜ーSHUHIN
●幸浜ーKOUHIN
●愛浜ーAIHIN
●明浜ーMEIHIN
●良浜ーRAUHIN
【B】
●彩浜ーSAIHIN
●梅浜ーMEIHIN
●永浜ーEIHIN
●海浜ー KAIHIN
●陽浜ーYUHIN
●優浜ーYUHIN
●結浜ーYUHIN
●桜浜ーOUHIN
●桃浜ーTOUHIN
●楓浜ーFUHIN
※アドベンチャーワールドで現在飼育しているジャイアントパンダ4頭(良浜、結浜、彩浜、楓浜)すべてを、2025年6月末ごろに中国に返すことが決まりました。アドベンチャーワールドではこの30年間で合わせて17頭のジャイアントパンダが誕生していて、「共同プロジェクトの継続を強く願っており、中国側と協議を続けていきます」としています。
和歌山県白浜町のテーマパーク・アドベンチャーワールドのパンダファミリー全20頭の写真入りの特別なフレーム切手をセットにしました。
【A】
●永明ーEIMEI
●蓉浜ーYOUHIN
●梅梅ーMEIMEI
●雄浜ーYUHIN
●隆浜ーRYUHIN
●秋浜ーSHUHIN
●幸浜ーKOUHIN
●愛浜ーAIHIN
●明浜ーMEIHIN
●良浜ーRAUHIN
【B】
●彩浜ーSAIHIN
●梅浜ーMEIHIN
●永浜ーEIHIN
●海浜ー KAIHIN
●陽浜ーYUHIN
●優浜ーYUHIN
●結浜ーYUHIN
●桜浜ーOUHIN
●桃浜ーTOUHIN
●楓浜ーFUHIN
※アドベンチャーワールドで現在飼育しているジャイアントパンダ4頭(良浜、結浜、彩浜、楓浜)すべてを、2025年6月末ごろに中国に返すことが決まりました。アドベンチャーワールドではこの30年間で合わせて17頭のジャイアントパンダが誕生していて、「共同プロジェクトの継続を強く願っており、中国側と協議を続けていきます」としています。
608681
近畿
神戸を包み込む光の彫刻「神戸ルミナリエ」。阪神・淡路大震災の後に定着した、神戸の冬の風物詩です。
ルミナリエはイタリア語が語源で、祝祭のためのイルミネーションという意味です。第30回の作品テーマは「30年の光、永遠に輝く希望」。
ルミナリエはイタリア語が語源で、祝祭のためのイルミネーションという意味です。第30回の作品テーマは「30年の光、永遠に輝く希望」。
608665
兵庫
「神戸のお嬢さま」の愛称で親しまれた神戸市立王子動物園のジャイアントパンダ「タンタン(旦旦)」が、2024年3月31日に国内最高齢の28歳で天国に旅立ちました。
いつでも笑顔をくれたタンタンをしのび、在りし日のタンタンの日常を収めた特別なフレーム切手です。
シート地には桜の木の下で寝転ぶ愛くるしい姿が採用されました。
いつでも笑顔をくれたタンタンをしのび、在りし日のタンタンの日常を収めた特別なフレーム切手です。
シート地には桜の木の下で寝転ぶ愛くるしい姿が採用されました。