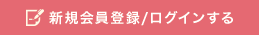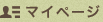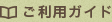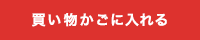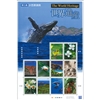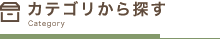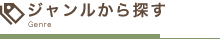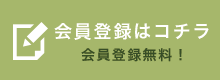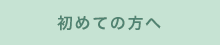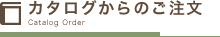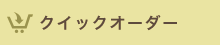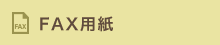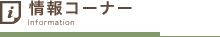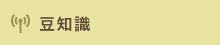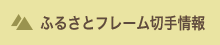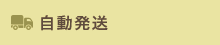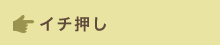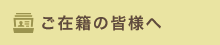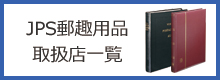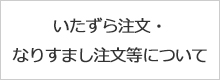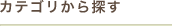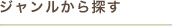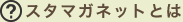世界遺産
122217
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
190518
【表紙】三重県の花(ハナショウブ)
【貨幣表面】熊野古道伊勢路
【地方自治法施行記念貨幣入りハードカバー切手帳】
ふるさと切手「地方自治法施行60周年記念シリーズ」5種シートと、政府発行「地方自治法施行60周年記念500円バイカラー・クラッド貨幣」をセットした、6ページだてハードカバー切手帳。サイズはヨコ約119×タテ約191×背幅約12ミリで、紙製ケース入り。発行数は「愛媛県」5800部・「山形県」・「三重県」は各5600部。
【バイカラー・クラッド貨幣】
2種類の異なる金属を組み合わせた「バイカラー」技術と、金属板を異なる種類の金属板で挟み込む「クラッド」技術を組み合わせた貨幣のこと。裏面の図案は全都道府県共通で、古銭のイメージ。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
【貨幣表面】熊野古道伊勢路
【地方自治法施行記念貨幣入りハードカバー切手帳】
ふるさと切手「地方自治法施行60周年記念シリーズ」5種シートと、政府発行「地方自治法施行60周年記念500円バイカラー・クラッド貨幣」をセットした、6ページだてハードカバー切手帳。サイズはヨコ約119×タテ約191×背幅約12ミリで、紙製ケース入り。発行数は「愛媛県」5800部・「山形県」・「三重県」は各5600部。
【バイカラー・クラッド貨幣】
2種類の異なる金属を組み合わせた「バイカラー」技術と、金属板を異なる種類の金属板で挟み込む「クラッド」技術を組み合わせた貨幣のこと。裏面の図案は全都道府県共通で、古銭のイメージ。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
604054
広島・四国
●瀬戸内しまのわ応援隊(愛媛県アイドル)ひめキュンフルーツ缶、(広島県アイドル)まなみのりさ(シート)
●厳島神社大鳥居
●岩城島 積善山の桜と夕日
●夕映えの多々羅大橋
●大崎下島 歴史の見える丘公園
●潮流体験来島海峡
●来島海峡大橋
●朝の三原沖
●鞆の浦 常夜灯
●松山市興居島 恋人峠
●松山市中島 泰ノ山から港をのぞむ
●厳島神社大鳥居
●岩城島 積善山の桜と夕日
●夕映えの多々羅大橋
●大崎下島 歴史の見える丘公園
●潮流体験来島海峡
●来島海峡大橋
●朝の三原沖
●鞆の浦 常夜灯
●松山市興居島 恋人峠
●松山市中島 泰ノ山から港をのぞむ
122163
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
122156
ガラパゴス諸島、タージ・マハル、ヴェネツィアとその潟、モシ・オ・トゥニャ/ヴィクトリアの滝、ケルン大聖堂。
※連刷には、シワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※連刷には、シワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
160834
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
122135
新シリーズ!
グランド・キャニオン国立公園、メンフィスとその墓地遺跡−ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯、モン-サン-ミシェルとその湾、マチュ・ピチュの歴史保護区、アンコール。
※連刷には、シワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
グランド・キャニオン国立公園、メンフィスとその墓地遺跡−ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯、モン-サン-ミシェルとその湾、マチュ・ピチュの歴史保護区、アンコール。
※連刷には、シワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
160821
日光東照宮陽明門、足利学校、きぶな、真岡鐵道SL、那須高原。シート地は、とちおとめ(イチゴ)。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
122119
2011年6月、中尊寺、毛越寺、観自在王院跡、無量光院跡及び金鶏山が世界遺産に登録された。
切手図案:
(1)中尊寺金色堂(こんじきどう):奥州藤原氏初代清衡(きよひら)が天治元(1124)年に上棟。堂の内外に金箔を押した「皆金色(かいこんじき)」の阿弥陀堂で、須弥檀(しゅみだん)内には初代清衡から四代泰衡(やすひら)までの遺体が安置されている。堂は昭和26(1951)年に国宝に、中尊寺境内は昭和54(1979)年に国の特別史跡にそれぞれ指定されている。
(2)中尊寺金銅華鬘(こんどうけまん):金色堂にかけられていた銅の表面に錬金した団扇形の華鬘。内輪系の内側には宝相華(ほうそうげ)唐草文様を透かし彫りにし、中央に総角結びの飾り紐、左右に迦陵頻伽(かりょうびんが)を掘り起こし、浄土世界を演出している。
(3)中尊寺経蔵:中尊寺境内にある間口3間、屋根は宝形、銅板葺き建物で、紺紙金銀字交書一切経(国宝)など中尊寺所蔵の貴重な経典を収納していた。
(4)毛越寺曲水の宴(もうつうじごくすいのえん):庭園の遣水(やりみず)に盃を浮かべ、流れに合わせて和歌を詠む、平安時代の優雅な歌遊び。現在では、毎年5月第4日曜日に開催。
(5)(6)毛越寺浄土庭園:二代基衡(もとひら)及び三代秀衡(ひでひら)により大伽藍が造営されたものの、その後の災禍により多くの建物を焼失。現在、「大泉が池」を中心とする浄土庭園と伽藍遺構が保存されており、国の特別史跡・特別名勝に指定されている。
(7)(8)観自在王院跡:二代基衡の妻が建立したといわれる寺院の跡。舞鶴が池を中心に荒磯様の石組、洲浜、中島、池の北岸には大小2つの阿弥陀堂跡などがある。日本庭園史上でも価値が高く「旧観自在王院庭園」として名勝に指定されている。
(9)無量光院跡と金鶏山(きんけいさん):三代秀衡が宇治の平等院鳳凰堂を模して建立した寺院の跡。南北に長い伽藍の中心線は、平泉の空間設計の基準となった金鶏山と直線で結ばれており、夕刻には背後の山並みに日が沈み、荘厳な極楽浄土の世界が体感できるように設計されていたと考えられる。
(10)中尊寺ハス:昭和25(1950)年に行われた奥州藤原氏の遺体調査において、四代泰衡の首級が納められていた桶から発見された約800年前のハスの種子を平成10(1998)年に開花させたもの。
シート地:中尊寺金色堂新覆堂(しんおおいどう)
金色堂全体を覆い風雨等から保護するため、正応元(1288)年に建設されたのが始めとされており、現在の覆堂(新覆堂)は昭和40(1965)年に建設。なお、室町時代中期に建設されたとされる旧覆堂も現存しており、国の重要文化財に指定されている。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
切手図案:
(1)中尊寺金色堂(こんじきどう):奥州藤原氏初代清衡(きよひら)が天治元(1124)年に上棟。堂の内外に金箔を押した「皆金色(かいこんじき)」の阿弥陀堂で、須弥檀(しゅみだん)内には初代清衡から四代泰衡(やすひら)までの遺体が安置されている。堂は昭和26(1951)年に国宝に、中尊寺境内は昭和54(1979)年に国の特別史跡にそれぞれ指定されている。
(2)中尊寺金銅華鬘(こんどうけまん):金色堂にかけられていた銅の表面に錬金した団扇形の華鬘。内輪系の内側には宝相華(ほうそうげ)唐草文様を透かし彫りにし、中央に総角結びの飾り紐、左右に迦陵頻伽(かりょうびんが)を掘り起こし、浄土世界を演出している。
(3)中尊寺経蔵:中尊寺境内にある間口3間、屋根は宝形、銅板葺き建物で、紺紙金銀字交書一切経(国宝)など中尊寺所蔵の貴重な経典を収納していた。
(4)毛越寺曲水の宴(もうつうじごくすいのえん):庭園の遣水(やりみず)に盃を浮かべ、流れに合わせて和歌を詠む、平安時代の優雅な歌遊び。現在では、毎年5月第4日曜日に開催。
(5)(6)毛越寺浄土庭園:二代基衡(もとひら)及び三代秀衡(ひでひら)により大伽藍が造営されたものの、その後の災禍により多くの建物を焼失。現在、「大泉が池」を中心とする浄土庭園と伽藍遺構が保存されており、国の特別史跡・特別名勝に指定されている。
(7)(8)観自在王院跡:二代基衡の妻が建立したといわれる寺院の跡。舞鶴が池を中心に荒磯様の石組、洲浜、中島、池の北岸には大小2つの阿弥陀堂跡などがある。日本庭園史上でも価値が高く「旧観自在王院庭園」として名勝に指定されている。
(9)無量光院跡と金鶏山(きんけいさん):三代秀衡が宇治の平等院鳳凰堂を模して建立した寺院の跡。南北に長い伽藍の中心線は、平泉の空間設計の基準となった金鶏山と直線で結ばれており、夕刻には背後の山並みに日が沈み、荘厳な極楽浄土の世界が体感できるように設計されていたと考えられる。
(10)中尊寺ハス:昭和25(1950)年に行われた奥州藤原氏の遺体調査において、四代泰衡の首級が納められていた桶から発見された約800年前のハスの種子を平成10(1998)年に開花させたもの。
シート地:中尊寺金色堂新覆堂(しんおおいどう)
金色堂全体を覆い風雨等から保護するため、正応元(1288)年に建設されたのが始めとされており、現在の覆堂(新覆堂)は昭和40(1965)年に建設。なお、室町時代中期に建設されたとされる旧覆堂も現存しており、国の重要文化財に指定されている。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
122118
2011年6月、北から聟島(むこじま)列島、父島列島、母島列島、火山(硫黄)列島のうち北硫黄島、南硫黄島及び西之島が世界自然遺産の区域として登録された。
切手図案:
(1)メグロ:母島列島に生息する小笠原村の村鳥。目の周りに三角の黒い模様があるのが特徴。
(2)ムニンノボタン:父島の固有種でわずかに自生。7〜8月に白い4枚の花弁をつけた花が咲く。
(3)ハートロック:父島の円縁湾に面した巨岩で、赤い岩肌がハートに見えることから、このように呼ばれている。
(4)オガサワラオカモノアラガイ:小笠原のみに生息する固有の陸産貝類で、現在は母島にのみ生息。ゼリーのような半透明の体に小さな殻を背負っている。
(5)扇池:南島にあり、隆起サンゴ礁が海水で浸食された後沈下して形成された沈水カルスト地形。
(6)ヒロベソカタマイマイの半化石:カタツムリの一種で約1000年前に絶滅したと言われてる。南島や南崎の砂丘上ではたくさんの半化石化した殻を見ることができる。
(7)ムニンヒメツバキ:父島の至る所で自生している小笠原村の村花。5〜6月に白い5枚の花弁をつけた花を咲かせる。現地では、ロースードとも呼ばれている。
(8)父島の林:父島には樹高の低い乾性低木林が広く分布しており、乾燥した気候に合わせて葉の大きさ、形が異なるなど、進化した固有植物が多数生育している。
(9)ミナミハンドウイルカ:小笠原諸島の周辺海域に生息。好奇心旺盛で人懐こく、一緒に泳ぐこともできる。丸みを帯び、やや短いくちばしが特徴。
(10)タコノキ:小笠原諸島の海岸付近に自生する固有の常緑高木で、小笠原村の村木。蛸の足のように気根が多数ある。
シート地:ザトウクジラ
夏場は北極海などで過ごし、冬場になると繁殖のために暖かい小笠原諸島周辺海域まで回遊して来る。ブリーチと呼ばれるジャンプなど様々なアクションで楽しませてくれる。また、「歌うクジラ」とも呼ばれ、繁殖期になると雄クジラが美しい鳴き声を出すことでも知られている。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
切手図案:
(1)メグロ:母島列島に生息する小笠原村の村鳥。目の周りに三角の黒い模様があるのが特徴。
(2)ムニンノボタン:父島の固有種でわずかに自生。7〜8月に白い4枚の花弁をつけた花が咲く。
(3)ハートロック:父島の円縁湾に面した巨岩で、赤い岩肌がハートに見えることから、このように呼ばれている。
(4)オガサワラオカモノアラガイ:小笠原のみに生息する固有の陸産貝類で、現在は母島にのみ生息。ゼリーのような半透明の体に小さな殻を背負っている。
(5)扇池:南島にあり、隆起サンゴ礁が海水で浸食された後沈下して形成された沈水カルスト地形。
(6)ヒロベソカタマイマイの半化石:カタツムリの一種で約1000年前に絶滅したと言われてる。南島や南崎の砂丘上ではたくさんの半化石化した殻を見ることができる。
(7)ムニンヒメツバキ:父島の至る所で自生している小笠原村の村花。5〜6月に白い5枚の花弁をつけた花を咲かせる。現地では、ロースードとも呼ばれている。
(8)父島の林:父島には樹高の低い乾性低木林が広く分布しており、乾燥した気候に合わせて葉の大きさ、形が異なるなど、進化した固有植物が多数生育している。
(9)ミナミハンドウイルカ:小笠原諸島の周辺海域に生息。好奇心旺盛で人懐こく、一緒に泳ぐこともできる。丸みを帯び、やや短いくちばしが特徴。
(10)タコノキ:小笠原諸島の海岸付近に自生する固有の常緑高木で、小笠原村の村木。蛸の足のように気根が多数ある。
シート地:ザトウクジラ
夏場は北極海などで過ごし、冬場になると繁殖のために暖かい小笠原諸島周辺海域まで回遊して来る。ブリーチと呼ばれるジャンプなど様々なアクションで楽しませてくれる。また、「歌うクジラ」とも呼ばれ、繁殖期になると雄クジラが美しい鳴き声を出すことでも知られている。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
160794
海越しの立山連峰、黒部ダム、ライチョウ、瑞龍寺、五箇山合掌造り集落。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
122091
ドイツとの共同発行!
両国の切手共通デザインの、レーゲンスブルク旧市街、薬師寺(いずれも世界遺産)、ほか。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
両国の切手共通デザインの、レーゲンスブルク旧市街、薬師寺(いずれも世界遺産)、ほか。
※未使用美品です。シートには、窓口販売時から発生していたシワ、ツメ跡などがある場合がございます。あらかじめご了承ください。