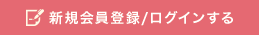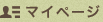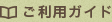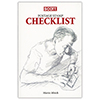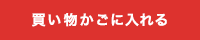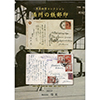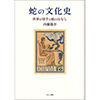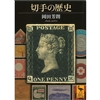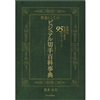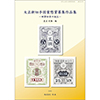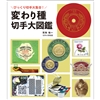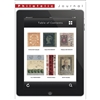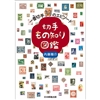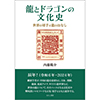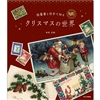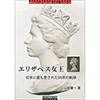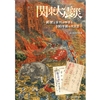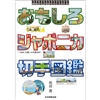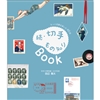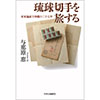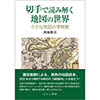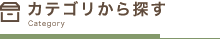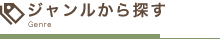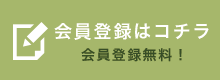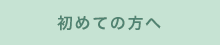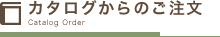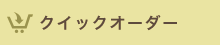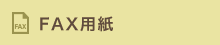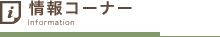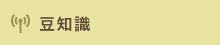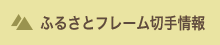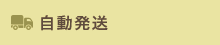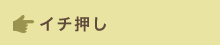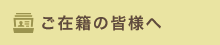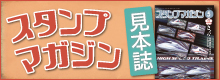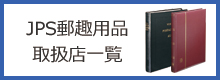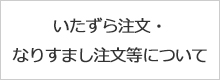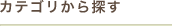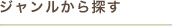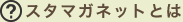�X��u�b�N
�؎��X�ւ̒m����[�߁A�y�������߂ɂȂ鏑�Ђł��B
�}�āA���s���A����i�X�^���v�j�A���j�A�f�[�^�W�ȂǁA���낢��Ȑ���Ő؎�E�X�ւ���鏑�Ђ����ł��B����Y��ǂ݂ӂ���P���ɏo��܂��B
445408
���ʂ��掟���i
�؎艚�ł̋����X���j�A�̌�p�҂̂ЂƂ�A�m���E�F�[�n�X�E�F�[�f���l�̐؎蒤���ƌ��f�U�C�i�[�A�}���e�B���E�����N�����{���܂�28�X���̂��߂ɐ��삵��1000������؎�A2023�N12�����܂ł̑S�؎�̃��X�g�i2024�N10�������j�B
�I�[���J���[�S110�y�[�W�B�\���T�C�Y�F154�~229�~���B�d��220��
���������ߐ�y2025�N�T��20���z���͂��\��U�����{�B
�؎艚�ł̋����X���j�A�̌�p�҂̂ЂƂ�A�m���E�F�[�n�X�E�F�[�f���l�̐؎蒤���ƌ��f�U�C�i�[�A�}���e�B���E�����N�����{���܂�28�X���̂��߂ɐ��삵��1000������؎�A2023�N12�����܂ł̑S�؎�̃��X�g�i2024�N10�������j�B
�I�[���J���[�S110�y�[�W�B�\���T�C�Y�F154�~229�~���B�d��220��
���������ߐ�y2025�N�T��20���z���͂��\��U�����{�B
8709
���j�̗�����ǂݎ�����
���Ė��B�ƌĂꂽ�������k���́A���V�A�i�\�A�j�E�����E���{�i���B���j���A���̎x�z�E���������߂Č������������n��ł���A�����ɕ~���ꂽ�S�����^�X�ֈ�i�S�X��j�̃R���N�V��������́A����E�n�悲�Ƃ̎匠�̕ϑJ�����邱�Ƃ��ł���B�P�Ȃ�S�X��R���N�V�����ł͂Ȃ��A�傫�ȗ��j�̗�����ǂݎ������B
�������a�j�E��
������
��2025�N2��1�����s
��A4���E�����^151�y�[�W�^�I�[���J���[
���Ė��B�ƌĂꂽ�������k���́A���V�A�i�\�A�j�E�����E���{�i���B���j���A���̎x�z�E���������߂Č������������n��ł���A�����ɕ~���ꂽ�S�����^�X�ֈ�i�S�X��j�̃R���N�V��������́A����E�n�悲�Ƃ̎匠�̕ϑJ�����邱�Ƃ��ł���B�P�Ȃ�S�X��R���N�V�����ł͂Ȃ��A�傫�ȗ��j�̗�����ǂݎ������B
�������a�j�E��
������
��2025�N2��1�����s
��A4���E�����^151�y�[�W�^�I�[���J���[
8708
���x�̕����j�V���[�Y��Q�e�I
�ւɊւ���l�X�ȃC���[�W�̗��j�I�E�Љ�I�w�i�ɂ��āA�؎����|����Ƃ��ēǂ݉����B���{�̋��݁A���ߓ�Ɍ���Ñォ��̎_�M����ɁA�C���h�A�t�@���I�ƃR�u���A���h�D�[�T�A�G�f���̉��Ƃ������A���E�e�n�̎փC���[�W��������A�u�ւƐ푈�v�͂ł͕č��Ɨ��푈���̊����猻��ɂ��ʂ��鎞��w�i�𖾂炩�ɂ���B
�������z��E��
�����ɂ����[��
��2025�N1��1�����s
��A5���E�����^240�y�[�W
�ւɊւ���l�X�ȃC���[�W�̗��j�I�E�Љ�I�w�i�ɂ��āA�؎����|����Ƃ��ēǂ݉����B���{�̋��݁A���ߓ�Ɍ���Ñォ��̎_�M����ɁA�C���h�A�t�@���I�ƃR�u���A���h�D�[�T�A�G�f���̉��Ƃ������A���E�e�n�̎փC���[�W��������A�u�ւƐ푈�v�͂ł͕č��Ɨ��푈���̊����猻��ɂ��ʂ��鎞��w�i�𖾂炩�ɂ���B
�������z��E��
�����ɂ����[��
��2025�N1��1�����s
��A5���E�����^240�y�[�W
8707
�y������b�ł��ǂ�؎�̗��j�I
�u�؎�̔����فv�̊w�|���A�c�ӗ������ɂ�������I
�u���E�ŏ��̐؎�͏����ɉ������ꂽ�H�v�u�����Ńk�[�h�؎肪��u���C�N�H�v�u12�̏��N��������1�Z���g�؎��50�N��ɂ͂�����ɂȂ����H�v�u���I�Ȋ�삩��c�t�ȋU���܂ŁA�؎�U�����l��`�v�E�E�E�v�킸�ǂ݂����Ȃ�l�X�Ȉ�b����A�Љ�w�i�Ǝ���J�ɉ�������u�؎�̐��E�j�v�B�{���̌��{��1976�N11���Ɋ��s����A���̂��ѕ��ɉ��ɂ��������������A�ꕔ�摜���ւ��ȂǏC�����s��ꂽ�B
�����c�F�N�E���^�c�ӗ����E���
���u�k�Њ�
��2024�N11��14�����s
���`�U���i���ɔ��j�E�����^424�y�[�W
�u�؎�̔����فv�̊w�|���A�c�ӗ������ɂ�������I
�u���E�ŏ��̐؎�͏����ɉ������ꂽ�H�v�u�����Ńk�[�h�؎肪��u���C�N�H�v�u12�̏��N��������1�Z���g�؎��50�N��ɂ͂�����ɂȂ����H�v�u���I�Ȋ�삩��c�t�ȋU���܂ŁA�؎�U�����l��`�v�E�E�E�v�킸�ǂ݂����Ȃ�l�X�Ȉ�b����A�Љ�w�i�Ǝ���J�ɉ�������u�؎�̐��E�j�v�B�{���̌��{��1976�N11���Ɋ��s����A���̂��ѕ��ɉ��ɂ��������������A�ꕔ�摜���ւ��ȂǏC�����s��ꂽ�B
�����c�F�N�E���^�c�ӗ����E���
���u�k�Њ�
��2024�N11��14�����s
���`�U���i���ɔ��j�E�����^424�y�[�W
8068
���x�e�������W�ƁE���،ܕv���ɂ�鎷�M�I
�킩��₷���X��p��Ɩ��i�̐}�ł��y�����؎�S�Ȏ��T�I
���i�ƌĂ��N���V�b�N�Ȑ��E�̐؎��͂����A�m���Ă������ł�����҂肠��ӂ�ȗX��p��Ȃǂ��A���[�t�W���X�^�C���i�؎�Ɖ�������Ղ��P�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��j�ʼn�������A���W�ƕK�g�̕S�Ȏ��T���a�����܂����I ���I���ꂽ95�̃L�[���[�h�̉���ŁA�؎���W�����y�����[������P���ł��B
�������Ƃ��������A���i�̊w�тɂ�
���i�A����e����ł��錾�t�ł��A���߂āu���̈Ӗ��������������ŊȌ��ɂ܂Ƃ߂�v�c�Ȃ�Č�����ƍ����Ă��܂����Ƃ��Ă���܂���ˁB�؎���W�Ƃ��悭�g���A�g�߂Ȃ�������������݂���X��p������l�ł��B������ƗX��p����m�F�������Ƃ��͂������A���i�̒m������ɂ��𗧂ǂݕ��Ƃ��Ċ��s���ꂽ���Ђ��{���ł��B
�����[�t��i���{������X�^�C��
�e�[�}�ƂȂ�95�̃L�[���[�h�A���ꂼ��𗝉�����̂ɍœK�Ȑ؎��g�p��i���ۂɗX�����ꂽ�����E�͂����ނȂǁj�����^���A������Ղ�����������P�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B�؎�W�Ō������郊�[�t�i�y�[�W�j�W���X�^�C���ł��B�؎��g�p��́A��ɃN���V�b�N��Z�~�N���V�b�N�i19���I�`20���I�O���j�̎���ɗp����ꂽ�A�i�������}�ł����S�ƂȂ��Ă��܂��B���[�t���̗��O�ɂ́A���W�|�C���g�⒍�ӎ����Ƃ�������t�L����Ă���Ƃ����\���ł��B
�@�؎�W�Ȃǂł́A�������܂Q�ς���̂Ŕ��Ă��܂��܂����A���̏��ЂȂ�茳�ł������Ɠ��e��ǂݍ��߂܂����A�C�ɂȂ����������m�F������A�ǂݕԂ����Ƃ��ł��܂��B���̊Ȍ��ɂ��ė������₷�����[�t����Ɖ���́A���x�e�������W�ƂƂ��Ēm���A�؎���W�Ƃ̃o�C�u���Ƃ��Ĉ��ǂ���Ă����w�������؎�̏W�ߕ��x�i1989�N�E���{�X��o�Ŋ��j�̒��ҁE���،ܕv���肪���Ă��܂��B
�y�{���̓��e�z
��P�́u���s�ړI�ʂ̐؎�v
���܂��܂Ȏg�p�ړI�̂��߂ɔ��s���ꂽ�A���E�e���̐؎�����Љ�I�X���x�ɂ͑��l�ȃT�[�r�X������܂��B���{�ł��A���B�E�����Ȃǂ̓���Ȏ�舵��������܂����A���E�ɂ͂���ɗl�X�Ȏg�p�ړI�̂��߂ɔ��s���ꂽ�؎肪���݂��܂��B���Ƃ��`�F�R�X���o�L�A���s�u�{�l�n�����p�؎�v�B�X�֕����m���ɁA�{�l�Ɏ�n������T�[�r�X�̂��߂ɔ��s���ꂽ�؎�ł��B���{�ɂ��u�{�l������X�ցv�Ƃ������x�͂���܂����A���̂��߂����̐�p�̐؎�͂���܂���B���̑��A�R�����r�A���s�u�����ؗp�؎�v�A�C�^���A���s�u�C���ǗX�֗p�؎�v�A�p�i�}���s�u���،��t�p�؎�v�ȂǁA���{�ɂ͑��݂��Ȃ��A���������s�ړI�̐؎�����Љ�Ă��܂��B
��Q�́u���E�̗X��p��v
�r�W���A���}�łŁA����ȗp����ڂŌ��Ă킩�邨�𗧂��y�[�W�I���̏͂̃|�C���g�́A���������̎����̂悤�ȗp��W�ł͂Ȃ��A���ׂĂ̗p��Ɏ��ۂ̐}�Ł@�|��ɃN���V�b�N�̖��i�|�@���\������Ă��邱�ƁB���ۂɁA�؎��}�e���A���i�����E�͂����Ȃǁj�̎p�`��A�g�����̎���𖼕i�Ŋm�F�ł���Ƃ����A����I�Ȏ��ʂł��B
�@�؎���W�̗��j�́A���E���̐؎�ł���y�j�[�E�u���b�N�ɒ[���A�܂��͉��Ă𒆐S�ɍL�܂��Ă����܂����B���̂��߉p���t�����X�ꂪ���ƂȂ����X��p�ꂪ���X����܂����A���Ƀt�����X�ꂪ�g���邱�Ƃ������A�����19���I�̗X��E�Ńt�����X�̉e�����傫���������Ƃ����R�Ȃ̂��Ƃ��B���i�Ȃɂ��Ȃ��g���Ă���u�ڑŁv��u���Łv�Ȃǂ̊�{�̗p�ꂩ��A�u�e�[�g�E�x�b�V���v�u���j�s�z�B�[�v�u�p�C�I�j�A�E�t���C�g�v�Ƃ������������I�ȗp��܂ŁA25�̌��I�����X��p����A�N���V�b�N�؎�̖��i������Ƃ��Ċm�F�ł�����e�ł��B
��R�́u�X�ւ͂����v
���E�ŏ��̕��ʂ͂������͂��߁A�m��ꂴ��͂����̊�{��������I�؎�ɔ�ׂĊS�������Ȃ肪���Ȃ͂����ł����A���E�ŏ��̕��ʂ͂�����A�e���̉����͂����A����Ȏ���̋M�d�Ȃ͂����Ȃǂɂ��ĉ�����Ă��܂��B
�@1869�N�ɃI�[�X�g���A�Ŕ��s���ꂽ���ʂ͂����i�����p�j���A���E�ŏ��̂͂����̗�ƂȂ�܂����B�؎蔭�s�ł́A�y�j�[�E�u���b�N����31�N��Əo�x�ꂽ���{���A�͂����ɂ��Ă͂S�N���1873�N�ɔ��s���J�n���Ă��܂��B�{�͂ł́A��{�ƂȂ镁�ʂ͂����̂ق��ɁA�����͂����A�O�M�͂����A�L�O�͂����A�܂��A�O���ɂ����Ȃ��C���ǂ͂����Ȃǂ̒�����������܂߂Čf�ڂ��Ă��܂��B
��S�́u�N���V�b�N�̖��i���g�s�b�N�؎�v
�e�������̐؎�̂Ȃ�����I�肷����́A�H���Ŕ������u���E�̖��i�v��A�����[����b��E���`�N�����؎���܂Ƃ߂��u���E�̃g�s�b�N�؎�v���e�[�}�B�{�͂�75���k���̃��[�t���ڂ��Ă��܂����A����ł͖��i�؎�̍ו������ĂƂ�܂���B�����ŁA�؎�̈���Z�p��f�U�C���̏ڍׂ܂ł����y���݂���������悤�ɁA�؎�̊g��ʐ^���f�ڂ��Ă��܂��B�u���E�ŏ��̕H�`�؎�v���͂��߁A�u���W���u���̖ڐ؎�v�A�A�����J�u���̒��̋��v�Ȃǂ̐l�C�̍������i�؎���A������Ղ�����ƂƂ��Ɋӏ܂ł��܂��B
�@����ɁA����Z�p�҂ł͂Ȃ��C���������A�{���t�����X�̐؎���܂˂�100�ʃV�[�g���蒤���ł����Ƃ����G�s�\�[�h�����u�j���[�J���h�j�A�̈�Ԑ؎�v�A�o������̐؎�Ƃ��Ă͐��E�ŏ��Ƃ����u�R�����r�A�̒����^�؎�v�A�艟����Ő������ꂽ�u�N���^���̈�Ԑ؎�v�A�{�[�A�푈����ɋ}��𗽂����߂Ɉ�����ꂽ�u�}�t�F�L���O�̐ʐ^�؎�v�ȂǁA�������؎肪�ڔ������ł��B
��T�́u�q��؎�̖��i�v
�l�ނ̖��ł�������s�@���o�ꂷ��ƁA�����ɗX�֕������ւ̎g�p����������A������s�p�̗X�֕��ɓ\�t����ړI�Ŕ��s���ꂽ�̂��u�q��؎�v�ł��B���̌�A�q��X�ւ�����ւƂ��Ĕ��W����ƁA����ɑ����̖��͓I�ȍq��؎肪���s�����悤�ɂȂ�܂����B���̏͂ł́A���E�̎��W�Ƃ����ڂ����A���i�ƌĂ�郍�}�����ӂ��q��؎�����Љ�Ă��܂��B
�@1917�N�C�^���A���s�u���E�ŏ��̍q��؎�v�́A���[�}�E�g���m�Ԃ̎�����s�X�ւɓ��ڂ���X�֕��̂��߂����ɁA���B�؎�ɉ����i����Ɉ����������j���Ĕ��s����܂����B���̂ق��A�A�����J�̍q��؎�Ƃ��Ă͂�����݂́u24�Z���g�E�W�F�j�[�q��؎�v�A�����E�M���V���E���{�ł��ꂼ��ɔ��s���ꂽ�ŏ��̍q��؎�A��s�D�ɓ��ڂ����X�֕��ɓ\�t�����u�c�F�b�y�����q��؎�v�Ƃ������L���ǂ���ɉ����A�R�x���R�����r�A�̂����������������u��Q���q��؎�v��A�S�[���h�E���b�V���ɕ����p�̃j���[�M�j�A��1935�N�ɔ��s���ꂽ�u�����z�̍q��؎�v�Ȃǂ́A���j�̈��ʂ�����������q��؎�̖��i13�_�����Љ�Ă��܂��B
���������̗X��p��W���֗��I
�{�����C����95�̃L�[���[�h�ɉ����A�m���Ă���������ȗX��p����A�����łU�y�[�W�ɂ킽���čׂ����̘^���Ă��܂��B�\�����ŁA�킩��ɂ����p��ɂ��ẮA�Ȃ�ׂ��Q�l�}�ł��f�ڂ��Ă��邨�𗧂��y�[�W�ł��I
�����،ܕv�E��
���؎�̔����ي�
��2025�N�Q��10�����s
���a�T���^�����E120�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͐��쒆�̃C���[�W�ł��B
�킩��₷���X��p��Ɩ��i�̐}�ł��y�����؎�S�Ȏ��T�I
���i�ƌĂ��N���V�b�N�Ȑ��E�̐؎��͂����A�m���Ă������ł�����҂肠��ӂ�ȗX��p��Ȃǂ��A���[�t�W���X�^�C���i�؎�Ɖ�������Ղ��P�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��j�ʼn�������A���W�ƕK�g�̕S�Ȏ��T���a�����܂����I ���I���ꂽ95�̃L�[���[�h�̉���ŁA�؎���W�����y�����[������P���ł��B
�������Ƃ��������A���i�̊w�тɂ�
���i�A����e����ł��錾�t�ł��A���߂āu���̈Ӗ��������������ŊȌ��ɂ܂Ƃ߂�v�c�Ȃ�Č�����ƍ����Ă��܂����Ƃ��Ă���܂���ˁB�؎���W�Ƃ��悭�g���A�g�߂Ȃ�������������݂���X��p������l�ł��B������ƗX��p����m�F�������Ƃ��͂������A���i�̒m������ɂ��𗧂ǂݕ��Ƃ��Ċ��s���ꂽ���Ђ��{���ł��B
�����[�t��i���{������X�^�C��
�e�[�}�ƂȂ�95�̃L�[���[�h�A���ꂼ��𗝉�����̂ɍœK�Ȑ؎��g�p��i���ۂɗX�����ꂽ�����E�͂����ނȂǁj�����^���A������Ղ�����������P�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B�؎�W�Ō������郊�[�t�i�y�[�W�j�W���X�^�C���ł��B�؎��g�p��́A��ɃN���V�b�N��Z�~�N���V�b�N�i19���I�`20���I�O���j�̎���ɗp����ꂽ�A�i�������}�ł����S�ƂȂ��Ă��܂��B���[�t���̗��O�ɂ́A���W�|�C���g�⒍�ӎ����Ƃ�������t�L����Ă���Ƃ����\���ł��B
�@�؎�W�Ȃǂł́A�������܂Q�ς���̂Ŕ��Ă��܂��܂����A���̏��ЂȂ�茳�ł������Ɠ��e��ǂݍ��߂܂����A�C�ɂȂ����������m�F������A�ǂݕԂ����Ƃ��ł��܂��B���̊Ȍ��ɂ��ė������₷�����[�t����Ɖ���́A���x�e�������W�ƂƂ��Ēm���A�؎���W�Ƃ̃o�C�u���Ƃ��Ĉ��ǂ���Ă����w�������؎�̏W�ߕ��x�i1989�N�E���{�X��o�Ŋ��j�̒��ҁE���،ܕv���肪���Ă��܂��B
�y�{���̓��e�z
��P�́u���s�ړI�ʂ̐؎�v
���܂��܂Ȏg�p�ړI�̂��߂ɔ��s���ꂽ�A���E�e���̐؎�����Љ�I�X���x�ɂ͑��l�ȃT�[�r�X������܂��B���{�ł��A���B�E�����Ȃǂ̓���Ȏ�舵��������܂����A���E�ɂ͂���ɗl�X�Ȏg�p�ړI�̂��߂ɔ��s���ꂽ�؎肪���݂��܂��B���Ƃ��`�F�R�X���o�L�A���s�u�{�l�n�����p�؎�v�B�X�֕����m���ɁA�{�l�Ɏ�n������T�[�r�X�̂��߂ɔ��s���ꂽ�؎�ł��B���{�ɂ��u�{�l������X�ցv�Ƃ������x�͂���܂����A���̂��߂����̐�p�̐؎�͂���܂���B���̑��A�R�����r�A���s�u�����ؗp�؎�v�A�C�^���A���s�u�C���ǗX�֗p�؎�v�A�p�i�}���s�u���،��t�p�؎�v�ȂǁA���{�ɂ͑��݂��Ȃ��A���������s�ړI�̐؎�����Љ�Ă��܂��B
��Q�́u���E�̗X��p��v
�r�W���A���}�łŁA����ȗp����ڂŌ��Ă킩�邨�𗧂��y�[�W�I���̏͂̃|�C���g�́A���������̎����̂悤�ȗp��W�ł͂Ȃ��A���ׂĂ̗p��Ɏ��ۂ̐}�Ł@�|��ɃN���V�b�N�̖��i�|�@���\������Ă��邱�ƁB���ۂɁA�؎��}�e���A���i�����E�͂����Ȃǁj�̎p�`��A�g�����̎���𖼕i�Ŋm�F�ł���Ƃ����A����I�Ȏ��ʂł��B
�@�؎���W�̗��j�́A���E���̐؎�ł���y�j�[�E�u���b�N�ɒ[���A�܂��͉��Ă𒆐S�ɍL�܂��Ă����܂����B���̂��߉p���t�����X�ꂪ���ƂȂ����X��p�ꂪ���X����܂����A���Ƀt�����X�ꂪ�g���邱�Ƃ������A�����19���I�̗X��E�Ńt�����X�̉e�����傫���������Ƃ����R�Ȃ̂��Ƃ��B���i�Ȃɂ��Ȃ��g���Ă���u�ڑŁv��u���Łv�Ȃǂ̊�{�̗p�ꂩ��A�u�e�[�g�E�x�b�V���v�u���j�s�z�B�[�v�u�p�C�I�j�A�E�t���C�g�v�Ƃ������������I�ȗp��܂ŁA25�̌��I�����X��p����A�N���V�b�N�؎�̖��i������Ƃ��Ċm�F�ł�����e�ł��B
��R�́u�X�ւ͂����v
���E�ŏ��̕��ʂ͂������͂��߁A�m��ꂴ��͂����̊�{��������I�؎�ɔ�ׂĊS�������Ȃ肪���Ȃ͂����ł����A���E�ŏ��̕��ʂ͂�����A�e���̉����͂����A����Ȏ���̋M�d�Ȃ͂����Ȃǂɂ��ĉ�����Ă��܂��B
�@1869�N�ɃI�[�X�g���A�Ŕ��s���ꂽ���ʂ͂����i�����p�j���A���E�ŏ��̂͂����̗�ƂȂ�܂����B�؎蔭�s�ł́A�y�j�[�E�u���b�N����31�N��Əo�x�ꂽ���{���A�͂����ɂ��Ă͂S�N���1873�N�ɔ��s���J�n���Ă��܂��B�{�͂ł́A��{�ƂȂ镁�ʂ͂����̂ق��ɁA�����͂����A�O�M�͂����A�L�O�͂����A�܂��A�O���ɂ����Ȃ��C���ǂ͂����Ȃǂ̒�����������܂߂Čf�ڂ��Ă��܂��B
��S�́u�N���V�b�N�̖��i���g�s�b�N�؎�v
�e�������̐؎�̂Ȃ�����I�肷����́A�H���Ŕ������u���E�̖��i�v��A�����[����b��E���`�N�����؎���܂Ƃ߂��u���E�̃g�s�b�N�؎�v���e�[�}�B�{�͂�75���k���̃��[�t���ڂ��Ă��܂����A����ł͖��i�؎�̍ו������ĂƂ�܂���B�����ŁA�؎�̈���Z�p��f�U�C���̏ڍׂ܂ł����y���݂���������悤�ɁA�؎�̊g��ʐ^���f�ڂ��Ă��܂��B�u���E�ŏ��̕H�`�؎�v���͂��߁A�u���W���u���̖ڐ؎�v�A�A�����J�u���̒��̋��v�Ȃǂ̐l�C�̍������i�؎���A������Ղ�����ƂƂ��Ɋӏ܂ł��܂��B
�@����ɁA����Z�p�҂ł͂Ȃ��C���������A�{���t�����X�̐؎���܂˂�100�ʃV�[�g���蒤���ł����Ƃ����G�s�\�[�h�����u�j���[�J���h�j�A�̈�Ԑ؎�v�A�o������̐؎�Ƃ��Ă͐��E�ŏ��Ƃ����u�R�����r�A�̒����^�؎�v�A�艟����Ő������ꂽ�u�N���^���̈�Ԑ؎�v�A�{�[�A�푈����ɋ}��𗽂����߂Ɉ�����ꂽ�u�}�t�F�L���O�̐ʐ^�؎�v�ȂǁA�������؎肪�ڔ������ł��B
��T�́u�q��؎�̖��i�v
�l�ނ̖��ł�������s�@���o�ꂷ��ƁA�����ɗX�֕������ւ̎g�p����������A������s�p�̗X�֕��ɓ\�t����ړI�Ŕ��s���ꂽ�̂��u�q��؎�v�ł��B���̌�A�q��X�ւ�����ւƂ��Ĕ��W����ƁA����ɑ����̖��͓I�ȍq��؎肪���s�����悤�ɂȂ�܂����B���̏͂ł́A���E�̎��W�Ƃ����ڂ����A���i�ƌĂ�郍�}�����ӂ��q��؎�����Љ�Ă��܂��B
�@1917�N�C�^���A���s�u���E�ŏ��̍q��؎�v�́A���[�}�E�g���m�Ԃ̎�����s�X�ւɓ��ڂ���X�֕��̂��߂����ɁA���B�؎�ɉ����i����Ɉ����������j���Ĕ��s����܂����B���̂ق��A�A�����J�̍q��؎�Ƃ��Ă͂�����݂́u24�Z���g�E�W�F�j�[�q��؎�v�A�����E�M���V���E���{�ł��ꂼ��ɔ��s���ꂽ�ŏ��̍q��؎�A��s�D�ɓ��ڂ����X�֕��ɓ\�t�����u�c�F�b�y�����q��؎�v�Ƃ������L���ǂ���ɉ����A�R�x���R�����r�A�̂����������������u��Q���q��؎�v��A�S�[���h�E���b�V���ɕ����p�̃j���[�M�j�A��1935�N�ɔ��s���ꂽ�u�����z�̍q��؎�v�Ȃǂ́A���j�̈��ʂ�����������q��؎�̖��i13�_�����Љ�Ă��܂��B
���������̗X��p��W���֗��I
�{�����C����95�̃L�[���[�h�ɉ����A�m���Ă���������ȗX��p����A�����łU�y�[�W�ɂ킽���čׂ����̘^���Ă��܂��B�\�����ŁA�킩��ɂ����p��ɂ��ẮA�Ȃ�ׂ��Q�l�}�ł��f�ڂ��Ă��邨�𗧂��y�[�W�ł��I
�����،ܕv�E��
���؎�̔����ي�
��2025�N�Q��10�����s
���a�T���^�����E120�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͐��쒆�̃C���[�W�ł��B
8706
���ɋP���R���N�V����
�u���ې؎�W JAKARTA 2024�v�ŋ��܂ɋP�����R���N�V�����A�S128���[�t���f�ځB���[�t�{���͉p��\�L�����A�ȒP�ȓ��{�����t���B
�����R�O�Y�E��
���X�^���y�f�B�A��
��2024�N10��1�����s
��A4���E�����^156�y�[�W�^�I�[���J���[
�u���ې؎�W JAKARTA 2024�v�ŋ��܂ɋP�����R���N�V�����A�S128���[�t���f�ځB���[�t�{���͉p��\�L�����A�ȒP�ȓ��{�����t���B
�����R�O�Y�E��
���X�^���y�f�B�A��
��2024�N10��1�����s
��A4���E�����^156�y�[�W�^�I�[���J���[
8703
�����`���a�����̓S���E�w�̋L��
�������珺�a�����ɂ����č��ꂽ�A�e��S����w���ނƂ������m�N���i�ꕔ��ʐF�܂ށj�̎����G�t�����W�߂�����B�k�C�����瓌�k�A�֓��A�����n���܂ŁA�����{��Ƃ������̂ł܂Ƃ߂Ă���B
���O�a�O���E��
�����Ɩ{
��2024�N7�����s
���`�S���^�����E121�y�[�W�^�I�[���J���[
�������珺�a�����ɂ����č��ꂽ�A�e��S����w���ނƂ������m�N���i�ꕔ��ʐF�܂ށj�̎����G�t�����W�߂�����B�k�C�����瓌�k�A�֓��A�����n���܂ŁA�����{��Ƃ������̂ł܂Ƃ߂Ă���B
���O�a�O���E��
�����Ɩ{
��2024�N7�����s
���`�S���^�����E121�y�[�W�^�I�[���J���[
8696
�����c�V�łȂ�������E�E�E
�吳�Q�i1913�j�N�A�V�؎�}�Ă̌��܂ɉ��債��539�g1610�_�̍�i�����^�B��i�͂قڒ�E���E���̂R�z�ʂ̐}�ł��P�g�Ƃ��č\���B�R���̌��ʁA����ǂ̓c�V�����̍�i���؎�}�Ăɍ̗p�A�u�c�V�؎�v���a�������B
��������Y�E��
������
��2024�N6��1�����s
��A4���E�����^160�y�[�W�^�I�[���J���[
�吳�Q�i1913�j�N�A�V�؎�}�Ă̌��܂ɉ��債��539�g1610�_�̍�i�����^�B��i�͂قڒ�E���E���̂R�z�ʂ̐}�ł��P�g�Ƃ��č\���B�R���̌��ʁA����ǂ̓c�V�����̍�i���؎�}�Ăɍ̗p�A�u�c�V�؎�v���a�������B
��������Y�E��
������
��2024�N6��1�����s
��A4���E�����^160�y�[�W�^�I�[���J���[
8067
���E�L���̕ς���؎�R���N�^�[�ɂ��u�т�����؎�v��W���I
���ꂪ�؎�I�H ������؎�I�H�c����ȋ����ɖ������u�т�����؎�v���A�P���̐}�ӂɂȂ�܂����I19���I���猻��܂ŁA�n�ӍH�v���ӂ��u�т�����؎�v�̐��E���A���邾���ł��y�����؎�摜�ƂƂ��ɂ��Љ�܂��I
���E�ŏ��̐؎�u�y�j�[�E�u���b�N�v�́A�P�Ђ���19�~22mm�T�C�Y�̎��ЂƂ��Ĕ��s����܂����B���݂܂ŁA�X�֕��Ɏg���鐢�E�̐؎�̑������A���̃y�j�[�E�u���b�N�̐��@�ɏ����Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A���܂��܂Ȏ���◝�R�ŁA���̐��@��f�ށA��������Ȃǂ���傫���O�ꂽ�A���j�[�N�ŋ����[���u�ς���؎�v���o�ꂵ�܂��B�����͎����I�ȗ��R������A�Ӑ}�����ς���؎肪���s����Ă��܂������A�؎���W����Ƃ��čL�܂�ɂ�A���W�Ƃ���сA�v�킸���ڂ��Ă��܂��y�����ς���؎�A�u�т�����؎�v�����X�Ɣ��s�����悤�ɂȂ����̂ł��B
�{���ł́A�ς���؎�̎��W�Ƃł���r�q�T�ꂳ��̃R���N�V�������A�U�̏͂ɂ܂Ƃ߂Ă��Љ�Ă��܂��B����ɏ��͂ł́A�ς���؎�̗��j�ƕϑJ���A���ゲ�Ƃɏڂ���������Ă��܂��B�ς���؎�Ƃ����A���l�ŃG���^�[�e�C�������g���ɕx�؎�̐��X���̘^�����A�y�������ځE�m��ꂴ��g���r�A��t�̑�؎�}�ӂ��A���Ђ���ǂ��������B
�y�{���̓��e�z
�����́u�ς���؎�̕ϑJ�v
�ʔ����������ς���؎�A���̒a���Ɏ���ߒ�����j�A���ゲ�Ƃ̕ϑJ�Ȃǂ��A�܂Ƃ߂ĉ�����Ă��܂��B
����P�́u�ς�����`�̐؎�v
1853�N�A���{�ł͉Y��ɍ��D�����q�����N�ɁA�ό`�؎�̑�\�i�ł���O�p�`�̐؎肪�A�p�̂̊�]��ŏ��߂Ĕ��s����Ă��܂��B�O�p�`�Ƃ�����Ȍ`�ŁA�킴�킴���s���ꂽ���̗��R�Ƃ́c�H���̌�A�ό`�؎�͕H�`�A�ی`�A���p�`�A�ʂĂ͑�ނɊ֘A�Â����s��`�i�n�[�g�^�Ȃǁj�A�؎�V�[�g���̂��ό`�ȂǁA�����鎩�R������ɂ���܂����B��P�͂ł́A����ȓ���Ȍ`�������g�ό`�؎�̕ϑJ�h����̓I�Ȑ؎��p���ĉ������ƂƂ��ɁA����^�E�����^�E�������ƁA�؎�̑傫���ɂ����ڂ��Ă��܂��B
����Q�́u����ȑf�ނ̐؎�v
���E�ŏ��̓���f�ނ̐؎�́A1852�N�ɃC���h�Ŕ��s���ꂽ���X���̉~�`�؎�ł����B���ꂩ��50�N�ȏ���o�ēo�ꂵ���̂��A�n���K���[�̃A���~����p�����؎�ł��B���̌�A���ȋ�����┓�A����������H������S�����Ȃǂ̋������؎����ɁA���Ȃǂ̕z�ށA�y�J�y�J��������̃v���X�`�b�N���̉��w�f�ށA�A�S���A�����K���X���ƁA���܂��܂ȍH�v�Ǝ�����Â炵���A���W�Ƃ��y���܂��Ă����؎肪���s����Ă��܂��B
����R�́u����Ȉ���̐؎�v
1960�N��̐؎�u�[�������L���̕��X�́A�v�킸�u���������I�v�ƌ��������Ȃ�A����Ȉ���̐؎肪�e�[�}�ł��B�u�[�^���Ȃǂ��甭�s���ꂽ���̈���؎�́A���݂ł͗���30�R�}���̓��������炩�ɍČ��ł������ɒ��i���𐋂��܂����B�ԂƐ̎����ዾ�ł̂����Ɣ�яo�Č�����A�i�O���t�؎���A�����͘b��ɂȂ�܂����B�܂��A�����ɂ��p������z���O��������A�`���R���[�g�Ȃǂ̍��肪���鍁���������A�ÈłŌ���~���C���N����A�����C���N��覐Ε���ΎR�D�����������؎�ȂǁA����Z�p�ƂƂ��ɕω���������ς���؎���y���߂܂��B
����S�́u�ٕ����Y�t���ꂽ�؎�v
�؎�̑f�ނƈقȂ镨����\��t�����؎�̂��Ƃł��B2004�N�ɃI�[�X�g���A�����s�����A�N���X�^���E�K���X��\�t�����؎肪��삯�ł��B���̌�́A�A���̎�q�⋛�̃^���̔�i�I�j�A�|�f�ނ┿�D�؎�ɖ{���̔��̒f�Ђ�ڒ�����ȂǁA�����̐؎肪���X�Ɠo��B�p�������̂̃W���[�W�[���甭�s���ꂽ�؎�́A�Ȃ�Ɩ{���̃_�C�������h���I �ߔN�ł́A�k�d�c��X�}�z�A�g�̃`�b�v����Ȃǂ̃n�C�e�N�f�ޕt�����o�Ă��܂����B
����T�́u�A�C�f�A������؎�v
�푈��C���t���Ƃ����������ɁA�؎��Ȏ����؎���d�݂̑���Ƃ����ݕ���p�؎�Ɏn�܂�A�]����L�����p���邽�߂̍L������؎�Ƃ������A�����ɖ��������A�C�f�A�؎肩��A�Ⴄ�����m�������e�[�}��}�ĂŔ��s���鋤�����s�؎�A�̂��߂̂����t���؎�A�����ŃV�[����F��h���Đ؎���I���W�i����i�ɂł���c�h�x�؎�A���E���ŕ]�����Ă������h�J�؎�ȂǁA�^�ɂƂ���Ȃ��y�������z�ɂ݂����؎�������Ղ�Ƃ��Љ�Ă��܂��B
����U�́u�ʕ��d�l�̐؎�v
�؎�͂��������A�X�֗����O�[���ؖ�����؎��Ƃ��Ēa�����܂����B�؎��������ł��B�������A1973�N�Ƀu�[�^�����g���ɂ̕ς���؎�h�s���܂��B�����̍��̂▯�����y��^���������R�[�h�؎�ł��B�̉������̃\�m�V�[�g���ۂ��Ɛ؎�Ƃ��Ă��܂��Ƃ́A�Ȃ�đ�_�Ȕ��z�ł��傤�I ����ɂ́A�Ԃ������{�̕\���ɐ؎������������{�؎�A���̃p�Y���̂悤�ȑg�ݗ��Đ؎��܂莆�؎�ɉ����A�R���i�Ђ̎��ゾ���炱�����܂ꂽ�h���V�̃A�C�f�A�؎�A�}�X�N�؎���o��B�ߔN�ł́A�f�W�^���Z�p�ɂ��t�����l���t�����Í��؎�Ȃ�Ă����A�n�C�e�N�ς���؎�����s����Ă��܂��B
���r�q�T��E��
���؎�̔����ي�
��2024�N�V��20�����s
���a�T���^�����E120�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͐��쒆�̌��{�ł��B
���ꂪ�؎�I�H ������؎�I�H�c����ȋ����ɖ������u�т�����؎�v���A�P���̐}�ӂɂȂ�܂����I19���I���猻��܂ŁA�n�ӍH�v���ӂ��u�т�����؎�v�̐��E���A���邾���ł��y�����؎�摜�ƂƂ��ɂ��Љ�܂��I
���E�ŏ��̐؎�u�y�j�[�E�u���b�N�v�́A�P�Ђ���19�~22mm�T�C�Y�̎��ЂƂ��Ĕ��s����܂����B���݂܂ŁA�X�֕��Ɏg���鐢�E�̐؎�̑������A���̃y�j�[�E�u���b�N�̐��@�ɏ����Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A���܂��܂Ȏ���◝�R�ŁA���̐��@��f�ށA��������Ȃǂ���傫���O�ꂽ�A���j�[�N�ŋ����[���u�ς���؎�v���o�ꂵ�܂��B�����͎����I�ȗ��R������A�Ӑ}�����ς���؎肪���s����Ă��܂������A�؎���W����Ƃ��čL�܂�ɂ�A���W�Ƃ���сA�v�킸���ڂ��Ă��܂��y�����ς���؎�A�u�т�����؎�v�����X�Ɣ��s�����悤�ɂȂ����̂ł��B
�{���ł́A�ς���؎�̎��W�Ƃł���r�q�T�ꂳ��̃R���N�V�������A�U�̏͂ɂ܂Ƃ߂Ă��Љ�Ă��܂��B����ɏ��͂ł́A�ς���؎�̗��j�ƕϑJ���A���ゲ�Ƃɏڂ���������Ă��܂��B�ς���؎�Ƃ����A���l�ŃG���^�[�e�C�������g���ɕx�؎�̐��X���̘^�����A�y�������ځE�m��ꂴ��g���r�A��t�̑�؎�}�ӂ��A���Ђ���ǂ��������B
�y�{���̓��e�z
�����́u�ς���؎�̕ϑJ�v
�ʔ����������ς���؎�A���̒a���Ɏ���ߒ�����j�A���ゲ�Ƃ̕ϑJ�Ȃǂ��A�܂Ƃ߂ĉ�����Ă��܂��B
����P�́u�ς�����`�̐؎�v
1853�N�A���{�ł͉Y��ɍ��D�����q�����N�ɁA�ό`�؎�̑�\�i�ł���O�p�`�̐؎肪�A�p�̂̊�]��ŏ��߂Ĕ��s����Ă��܂��B�O�p�`�Ƃ�����Ȍ`�ŁA�킴�킴���s���ꂽ���̗��R�Ƃ́c�H���̌�A�ό`�؎�͕H�`�A�ی`�A���p�`�A�ʂĂ͑�ނɊ֘A�Â����s��`�i�n�[�g�^�Ȃǁj�A�؎�V�[�g���̂��ό`�ȂǁA�����鎩�R������ɂ���܂����B��P�͂ł́A����ȓ���Ȍ`�������g�ό`�؎�̕ϑJ�h����̓I�Ȑ؎��p���ĉ������ƂƂ��ɁA����^�E�����^�E�������ƁA�؎�̑傫���ɂ����ڂ��Ă��܂��B
����Q�́u����ȑf�ނ̐؎�v
���E�ŏ��̓���f�ނ̐؎�́A1852�N�ɃC���h�Ŕ��s���ꂽ���X���̉~�`�؎�ł����B���ꂩ��50�N�ȏ���o�ēo�ꂵ���̂��A�n���K���[�̃A���~����p�����؎�ł��B���̌�A���ȋ�����┓�A����������H������S�����Ȃǂ̋������؎����ɁA���Ȃǂ̕z�ށA�y�J�y�J��������̃v���X�`�b�N���̉��w�f�ށA�A�S���A�����K���X���ƁA���܂��܂ȍH�v�Ǝ�����Â炵���A���W�Ƃ��y���܂��Ă����؎肪���s����Ă��܂��B
����R�́u����Ȉ���̐؎�v
1960�N��̐؎�u�[�������L���̕��X�́A�v�킸�u���������I�v�ƌ��������Ȃ�A����Ȉ���̐؎肪�e�[�}�ł��B�u�[�^���Ȃǂ��甭�s���ꂽ���̈���؎�́A���݂ł͗���30�R�}���̓��������炩�ɍČ��ł������ɒ��i���𐋂��܂����B�ԂƐ̎����ዾ�ł̂����Ɣ�яo�Č�����A�i�O���t�؎���A�����͘b��ɂȂ�܂����B�܂��A�����ɂ��p������z���O��������A�`���R���[�g�Ȃǂ̍��肪���鍁���������A�ÈłŌ���~���C���N����A�����C���N��覐Ε���ΎR�D�����������؎�ȂǁA����Z�p�ƂƂ��ɕω���������ς���؎���y���߂܂��B
����S�́u�ٕ����Y�t���ꂽ�؎�v
�؎�̑f�ނƈقȂ镨����\��t�����؎�̂��Ƃł��B2004�N�ɃI�[�X�g���A�����s�����A�N���X�^���E�K���X��\�t�����؎肪��삯�ł��B���̌�́A�A���̎�q�⋛�̃^���̔�i�I�j�A�|�f�ނ┿�D�؎�ɖ{���̔��̒f�Ђ�ڒ�����ȂǁA�����̐؎肪���X�Ɠo��B�p�������̂̃W���[�W�[���甭�s���ꂽ�؎�́A�Ȃ�Ɩ{���̃_�C�������h���I �ߔN�ł́A�k�d�c��X�}�z�A�g�̃`�b�v����Ȃǂ̃n�C�e�N�f�ޕt�����o�Ă��܂����B
����T�́u�A�C�f�A������؎�v
�푈��C���t���Ƃ����������ɁA�؎��Ȏ����؎���d�݂̑���Ƃ����ݕ���p�؎�Ɏn�܂�A�]����L�����p���邽�߂̍L������؎�Ƃ������A�����ɖ��������A�C�f�A�؎肩��A�Ⴄ�����m�������e�[�}��}�ĂŔ��s���鋤�����s�؎�A�̂��߂̂����t���؎�A�����ŃV�[����F��h���Đ؎���I���W�i����i�ɂł���c�h�x�؎�A���E���ŕ]�����Ă������h�J�؎�ȂǁA�^�ɂƂ���Ȃ��y�������z�ɂ݂����؎�������Ղ�Ƃ��Љ�Ă��܂��B
����U�́u�ʕ��d�l�̐؎�v
�؎�͂��������A�X�֗����O�[���ؖ�����؎��Ƃ��Ēa�����܂����B�؎��������ł��B�������A1973�N�Ƀu�[�^�����g���ɂ̕ς���؎�h�s���܂��B�����̍��̂▯�����y��^���������R�[�h�؎�ł��B�̉������̃\�m�V�[�g���ۂ��Ɛ؎�Ƃ��Ă��܂��Ƃ́A�Ȃ�đ�_�Ȕ��z�ł��傤�I ����ɂ́A�Ԃ������{�̕\���ɐ؎������������{�؎�A���̃p�Y���̂悤�ȑg�ݗ��Đ؎��܂莆�؎�ɉ����A�R���i�Ђ̎��ゾ���炱�����܂ꂽ�h���V�̃A�C�f�A�؎�A�}�X�N�؎���o��B�ߔN�ł́A�f�W�^���Z�p�ɂ��t�����l���t�����Í��؎�Ȃ�Ă����A�n�C�e�N�ς���؎�����s����Ă��܂��B
���r�q�T��E��
���؎�̔����ي�
��2024�N�V��20�����s
���a�T���^�����E120�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͐��쒆�̌��{�ł��B
8695
�I�[���J���[��厏�̑�13�e
�����O�X��Ƃ̗D�ꂽ�������ʂ��I�[���J���[���^������厏�̑�13�e�A�S�U�e���^�B
�E�R���D���u�ʘZ�u�q�v�R�ł̊m��Ǝ蒤�؎萻���̘b�v
�E�c�D�}�C���[�z�t�u���[���V���X�̒��i�v
�E�v�D�O�����g�}���u�݃����S�� ���V�A�X�ǁv
�E�x�D�t�F���g�����u�x���M�[�A���_���I�����s�����̃t�����X�Ƃ̗X�ցv
�E���c�^�O�u�ϑ��X�� 1930-1941�v
�E�Փ��Y�F�u���ۓW�e�[�}�e�B�N�ł̃t���[���g��Ƌ��܂ւ̃X�R�A�A�b�v���H��v
���g�c�h�E��
���X�^���y�f�B�A��
��2023�N12��30�����s
��A4���E�����^142�y�[�W�^�I�[���J���[
�����O�X��Ƃ̗D�ꂽ�������ʂ��I�[���J���[���^������厏�̑�13�e�A�S�U�e���^�B
�E�R���D���u�ʘZ�u�q�v�R�ł̊m��Ǝ蒤�؎萻���̘b�v
�E�c�D�}�C���[�z�t�u���[���V���X�̒��i�v
�E�v�D�O�����g�}���u�݃����S�� ���V�A�X�ǁv
�E�x�D�t�F���g�����u�x���M�[�A���_���I�����s�����̃t�����X�Ƃ̗X�ցv
�E���c�^�O�u�ϑ��X�� 1930-1941�v
�E�Փ��Y�F�u���ۓW�e�[�}�e�B�N�ł̃t���[���g��Ƌ��܂ւ̃X�R�A�A�b�v���H��v
���g�c�h�E��
���X�^���y�f�B�A��
��2023�N12��30�����s
��A4���E�����^142�y�[�W�^�I�[���J���[
8168
���߂Ēm��I��Ԑ؎�50�̐��E
���E�ň�ԍŏ��Ɂu�؎�v�ɕ`���ꂽ���܂��܂ȃf�U�C������A50�̃e�[�}�����I���āA�؎�ɂ܂��m��ꂴ����j��G�s�\�[�h��X�֊w�ҁE�����z���������܂��B
�u�����ƐA���v�u�Ȋw�Z�p�v�u�Љ�ƕ����v�u�_�b�^�`���Ə@���v�̂S�͗��ĂŁA���A�L�A�F���J���A��s�@�A�N���X�}�X�Ƃ������e�[�}�ŁA���߂ĕ`���ꂽ�؎�}�Ăɂ܂���b�A�v�������Ȃ����s�Ɏ���w�i�ɉ����A�V�[���J���X��e���r�A�x�@���A�^�g�D�[�A�鐂Ƃ������A�����Ƌ����ӊO�ȃe�[�}�̈�Ԑ؎���o�ꂵ�܂��I
�������z��E��
�����{�X��o�Ŋ�
��2024�N5��1�����s
���`�T���^�����E112�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͍쐬�r���̌��{�ł��B
���E�ň�ԍŏ��Ɂu�؎�v�ɕ`���ꂽ���܂��܂ȃf�U�C������A50�̃e�[�}�����I���āA�؎�ɂ܂��m��ꂴ����j��G�s�\�[�h��X�֊w�ҁE�����z���������܂��B
�u�����ƐA���v�u�Ȋw�Z�p�v�u�Љ�ƕ����v�u�_�b�^�`���Ə@���v�̂S�͗��ĂŁA���A�L�A�F���J���A��s�@�A�N���X�}�X�Ƃ������e�[�}�ŁA���߂ĕ`���ꂽ�؎�}�Ăɂ܂���b�A�v�������Ȃ����s�Ɏ���w�i�ɉ����A�V�[���J���X��e���r�A�x�@���A�^�g�D�[�A�鐂Ƃ������A�����Ƌ����ӊO�ȃe�[�}�̈�Ԑ؎���o�ꂵ�܂��I
�������z��E��
�����{�X��o�Ŋ�
��2024�N5��1�����s
���`�T���^�����E112�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͍쐬�r���̌��{�ł��B
8694
�X�֊w�҂������̗�����ɁA���{�A���N�A�����A����A�W�A�A�L���X�g�����E�ȂǁA���E�̗��ɂ��āA���̃x�[�X�ƂȂ镶���j�⋻���[���G�s�\�[�h�Ȃǂ��A�؎�ƂƂ��ɏЉ��B
�������z��E��
�����ɂ����[��
��2024�N1��1�����s
��A5���E�����^204�y�[�W
�������z��E��
�����ɂ����[��
��2024�N1��1�����s
��A5���E�����^204�y�[�W
8066
�؎��J�[�h�A�����ȂǑ��푽�l�ȃ��m��ʂ��Č����u�N���X�}�X�v�̒m��ꂴ��G�s�\�[�h�I
�N���X�}�X�ɂ��Ă̂��܂��܂Ȓm���◠�b�Ȃǂ��A�A���e�B�[�N�ȃN���X�}�X�J�[�h��؎���͂��߁A�����J�o�[������J�o�[�A�L�O����A�������i�t�@���V�[�L�����Z���j�A���[�^�[�X�^���v�ȂǑ��푽�l�ȃ}�e���A���ł��Љ�I
�{�����e
����P�́u�N���X�}�X�̂Ђ݂v
�L���X�g�����܂ꂽ�͔̂n��������Ȃ��H
����Q�́u�݂�Ȃ̂Ƃ����� �T���^�N���[�X�v
������ϖ����ȃT���^�I
����R�́u����ԃg�i�J�C�v
�g�i�J�C�͂����������̂��H
����S�́u�k�̍����烁���[�N���X�}�X�I�v
�k���ɓ`���N���X�}�X�̃��[�c�I
����T�́u�N���X�}�X�c���[�̂Ђ݂v
�푈���L�߂��c���[�H
����U�́u�N���X�}�X�ɓo�ꂷ�铮���v
�����������A�݂�ȏW�܂�I
����V�́u�N���X�}�X�̐H�ו��v
���{�ł̓`�L���A�ł��k���ł́H
����W�́u�N���X�}�X�ɓo�ꂷ��A�C�e���v
�c���[�ɂ悭��������̂ł��I
����X�́u�J�[�h�Ɛ؎�Ŋy���ރN���X�}�X�v
�N���X�}�X�J�[�h�̎n�܂���āH
���ؑ����T�E��
���؎�̔����ي�
��2023�N11��20�����s
���a�T���ό`�^�����E112�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͍쐬�r���̌��{�ł��B
�N���X�}�X�ɂ��Ă̂��܂��܂Ȓm���◠�b�Ȃǂ��A�A���e�B�[�N�ȃN���X�}�X�J�[�h��؎���͂��߁A�����J�o�[������J�o�[�A�L�O����A�������i�t�@���V�[�L�����Z���j�A���[�^�[�X�^���v�ȂǑ��푽�l�ȃ}�e���A���ł��Љ�I
�{�����e
����P�́u�N���X�}�X�̂Ђ݂v
�L���X�g�����܂ꂽ�͔̂n��������Ȃ��H
����Q�́u�݂�Ȃ̂Ƃ����� �T���^�N���[�X�v
������ϖ����ȃT���^�I
����R�́u����ԃg�i�J�C�v
�g�i�J�C�͂����������̂��H
����S�́u�k�̍����烁���[�N���X�}�X�I�v
�k���ɓ`���N���X�}�X�̃��[�c�I
����T�́u�N���X�}�X�c���[�̂Ђ݂v
�푈���L�߂��c���[�H
����U�́u�N���X�}�X�ɓo�ꂷ�铮���v
�����������A�݂�ȏW�܂�I
����V�́u�N���X�}�X�̐H�ו��v
���{�ł̓`�L���A�ł��k���ł́H
����W�́u�N���X�}�X�ɓo�ꂷ��A�C�e���v
�c���[�ɂ悭��������̂ł��I
����X�́u�J�[�h�Ɛ؎�Ŋy���ރN���X�}�X�v
�N���X�}�X�J�[�h�̎n�܂���āH
���ؑ����T�E��
���؎�̔����ي�
��2023�N11��20�����s
���a�T���ό`�^�����E112�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͍쐬�r���̌��{�ł��B
8043
�؎�r�W���A���q�X�g���[�E�V���[�Y��S�e�I
���E�ōł������؎�ɕ`���ꂽ�N��A�G���U�x�X�����̐��U��؎�ł��ǂ�I
�G���U�x�X������70�N�Ƃ����݈ʊ��Ԃɉ����A�{���ƃR�����E�F���X�i���p�A�M�����j�Ƃ����L��Ȓn��̎Ƃ��āA�����_�ŌÍ������̒N���������̐؎�ɕ`���ꂽ�N�傾�Ƃ�����ł��傤�B����ȏ����É���96�N�ɂ킽�鐶�U���A�؎�⑽�ʂȃ}�e���A���ƂƂ��ɂ��ǂ�Ȃ���A�C�M���X�؎�̗��j�E�i�i�E�����������\�ł���P���ł��B�܂��A�R�����ł̓��B�N�g���A�����ȍ~�̗�㍑�������̎���̕��ʐ؎�ɂ��Ă��A�ڂ���������Ă��܂��B
���R�c����E��
�i�C�M���X�؎���W�Ɓ^���v���c�@�l���{�X�������j
�����{�X��o�Ŋ�
��2023�N11��10�����s
���`�T���^�����E128�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͍쐬�r���̌��{�ł��B
�u�G���U�x�X�����֘A�؎�v���������ł��ē����Ă��܂��B
���E�ōł������؎�ɕ`���ꂽ�N��A�G���U�x�X�����̐��U��؎�ł��ǂ�I
�G���U�x�X������70�N�Ƃ����݈ʊ��Ԃɉ����A�{���ƃR�����E�F���X�i���p�A�M�����j�Ƃ����L��Ȓn��̎Ƃ��āA�����_�ŌÍ������̒N���������̐؎�ɕ`���ꂽ�N�傾�Ƃ�����ł��傤�B����ȏ����É���96�N�ɂ킽�鐶�U���A�؎�⑽�ʂȃ}�e���A���ƂƂ��ɂ��ǂ�Ȃ���A�C�M���X�؎�̗��j�E�i�i�E�����������\�ł���P���ł��B�܂��A�R�����ł̓��B�N�g���A�����ȍ~�̗�㍑�������̎���̕��ʐ؎�ɂ��Ă��A�ڂ���������Ă��܂��B
���R�c����E��
�i�C�M���X�؎���W�Ɓ^���v���c�@�l���{�X�������j
�����{�X��o�Ŋ�
��2023�N11��10�����s
���`�T���^�����E128�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͍쐬�r���̌��{�ł��B
�u�G���U�x�X�����֘A�؎�v���������ł��ē����Ă��܂��B
8167
100�N�O�A���\�L�̑�ЊQ�����т��l�X�̐��X�������t���`����u�֓���k�Ёv�I
1923�N�X���P���ߑO11��58���B��֓��𒆐S�ɐr��Ȕ�Q�������炵���֓���k�Ђ���A���N��100�N���}���܂��B�����̔�Ў҂����̐��X�����莆��e�펑����ʂ��A���܂łɂȂ��V���Ȏ��_�ŁA���\�L�̑�ЊQ�̃��A���Ȏp��U��Ԃ鏑�Ђ��a�����܂����B
�֓���k�ЂɊւ���吳�����̂��܂��܂Ȋ�����������A��Q�������ɒǂ����V���E�G���ށA�^�ɔ���}�G�A�����Ďs��̐l�X�́g ���̐��h�Ƃ����鐔�����̎莆�c�����������Ƃ��āA�{���͂U�̏͂ɂ��A�u�֓���k�Ёv�̎p������ɂ��Ă��܂��B
����P�́u�X�ւ������֓���k�Ђ̂P�����v
�Ȃ�Ƒ�k�Д�������ɍ����o���ꂽ�莆�i�X���P���ߌ�V�`�W���Ɉ���j����A�����A���X���A�R����A�T����c�ƁA�قڂP�����Ԃɍ����o���ꂽ�X�֕����A���̕��ʂƂƂ��Ɏ��n��ŏЉ�čs���܂��B��Ђ����l�X�����M�����g�k�Ѓh�L�������^���[�E���|�[�g�h�Ƃ�����ł��傤�B�܂��A�n�k��������̔z�B��A��Ў҂ւ̋~�ϑ[�u�i�����d��E��ЗX�֓��j���Ƃ����X�ǂ̑Ή����A�����̗X�֕�����ǂ݉����čs���܂��B
����Q�́u�G�͂����Ō���֓���k�Ёv
����R�́u�֓���k�Ђ�`���唻�}�v
�Տꊴ���ӂ��r�W���A�������A�u�G�͂����v�Ɓu�唻�}�v�Ŋ֓���k�Ђ̔�Џ�������܂��B���݂̓e���r���p��C���^�[�l�b�g�ŁA���̂�ЊQ�̃j���[�X�����A���^�C���Œm�邱�Ƃ��ł��܂����A�����̏d�v�ȃr�W���A���E�R���e���c�́A�u�G�͂����v��Δłň�����ꂽ�u�唻�}�v�ł����B�p�ЂƉ�������s�E�����A�V�ɂ��͂��Ή��̑嗳���B�����Ƃ��Ă͍ő��̎��o��S���֎��m����A����ɂ�100�N��̎������ɂƂ��Ă��M�d�ȗ��j�����ƂȂ��Ă��܂��B
����S�́u�����ւ̉e���E�����v
�������s�����ǐV������I�ȕ����E���ނƂ��������������𒆐S�ɁA�����ւ̉e���Ɛ��{�̑���܂Ƃ߂܂����B������ƒ����������ɁA�u�V�c�É�����̉������̍����v������܂��B���͖����ȗ��A���݂���ЊQ�̐܂ɂ́A�V�c�É����牶�����i���������j���͂����Ă��邻���ł��B
����T�́u�X�ւȂǂւ̎b��Ή��v
�n�k�ɂ���Ĉ���ǂ��ɂ̐؎���Ă��Ă��܂������߁A�b��Ŕ��s���ꂽ�k�А؎��͂����A�ɂ��āA���g�p�E�g�p��E�V�[�g�E�G���[�����o���G�e�B�L���ɏЉ�B�܂��A�啔�����Ď��������Ƃŕs���s�ƂȂ�A�����킸���Ɍ�������H���ȁu���{�䍥�V�L�O�؎�v�ɂ��Ă�������Ă��܂��B
����U�́u�֓���k�Ђ���̕����v
��k�Ђ���̕������e�[�}�ł��B�W����A�Ă��쌴��V���ɋ�搮�����������n�}�A������12�N��ɊJ�Â��ꂽ�u�����L�O���l�唎����v�܂ł́A�����̋O�Ղ����ǂ�܂��B
�؎�ƗX�ցA�����Ċe�펑���ɂ���ĐV���Ȏ��_����u�֓���k�Ёv�����������A���܂łɗނ̂Ȃ����Ђł��B�M�d�Ȏ������疾�炩�ɂȂ��ЊQ�̎��ԁA���ЁA����lj������I
���k�ЗX�����E��
�����{�X��o�Ŋ�
��2023�N�X���P�����s
���a�T���E�����^96�y�[�W�^�I�[���J���[
���\���E���ʂ͐��쒆�̃C���[�W�ł��B
1923�N�X���P���ߑO11��58���B��֓��𒆐S�ɐr��Ȕ�Q�������炵���֓���k�Ђ���A���N��100�N���}���܂��B�����̔�Ў҂����̐��X�����莆��e�펑����ʂ��A���܂łɂȂ��V���Ȏ��_�ŁA���\�L�̑�ЊQ�̃��A���Ȏp��U��Ԃ鏑�Ђ��a�����܂����B
�֓���k�ЂɊւ���吳�����̂��܂��܂Ȋ�����������A��Q�������ɒǂ����V���E�G���ށA�^�ɔ���}�G�A�����Ďs��̐l�X�́g ���̐��h�Ƃ����鐔�����̎莆�c�����������Ƃ��āA�{���͂U�̏͂ɂ��A�u�֓���k�Ёv�̎p������ɂ��Ă��܂��B
����P�́u�X�ւ������֓���k�Ђ̂P�����v
�Ȃ�Ƒ�k�Д�������ɍ����o���ꂽ�莆�i�X���P���ߌ�V�`�W���Ɉ���j����A�����A���X���A�R����A�T����c�ƁA�قڂP�����Ԃɍ����o���ꂽ�X�֕����A���̕��ʂƂƂ��Ɏ��n��ŏЉ�čs���܂��B��Ђ����l�X�����M�����g�k�Ѓh�L�������^���[�E���|�[�g�h�Ƃ�����ł��傤�B�܂��A�n�k��������̔z�B��A��Ў҂ւ̋~�ϑ[�u�i�����d��E��ЗX�֓��j���Ƃ����X�ǂ̑Ή����A�����̗X�֕�����ǂ݉����čs���܂��B
����Q�́u�G�͂����Ō���֓���k�Ёv
����R�́u�֓���k�Ђ�`���唻�}�v
�Տꊴ���ӂ��r�W���A�������A�u�G�͂����v�Ɓu�唻�}�v�Ŋ֓���k�Ђ̔�Џ�������܂��B���݂̓e���r���p��C���^�[�l�b�g�ŁA���̂�ЊQ�̃j���[�X�����A���^�C���Œm�邱�Ƃ��ł��܂����A�����̏d�v�ȃr�W���A���E�R���e���c�́A�u�G�͂����v��Δłň�����ꂽ�u�唻�}�v�ł����B�p�ЂƉ�������s�E�����A�V�ɂ��͂��Ή��̑嗳���B�����Ƃ��Ă͍ő��̎��o��S���֎��m����A����ɂ�100�N��̎������ɂƂ��Ă��M�d�ȗ��j�����ƂȂ��Ă��܂��B
����S�́u�����ւ̉e���E�����v
�������s�����ǐV������I�ȕ����E���ނƂ��������������𒆐S�ɁA�����ւ̉e���Ɛ��{�̑���܂Ƃ߂܂����B������ƒ����������ɁA�u�V�c�É�����̉������̍����v������܂��B���͖����ȗ��A���݂���ЊQ�̐܂ɂ́A�V�c�É����牶�����i���������j���͂����Ă��邻���ł��B
����T�́u�X�ւȂǂւ̎b��Ή��v
�n�k�ɂ���Ĉ���ǂ��ɂ̐؎���Ă��Ă��܂������߁A�b��Ŕ��s���ꂽ�k�А؎��͂����A�ɂ��āA���g�p�E�g�p��E�V�[�g�E�G���[�����o���G�e�B�L���ɏЉ�B�܂��A�啔�����Ď��������Ƃŕs���s�ƂȂ�A�����킸���Ɍ�������H���ȁu���{�䍥�V�L�O�؎�v�ɂ��Ă�������Ă��܂��B
����U�́u�֓���k�Ђ���̕����v
��k�Ђ���̕������e�[�}�ł��B�W����A�Ă��쌴��V���ɋ�搮�����������n�}�A������12�N��ɊJ�Â��ꂽ�u�����L�O���l�唎����v�܂ł́A�����̋O�Ղ����ǂ�܂��B
�؎�ƗX�ցA�����Ċe�펑���ɂ���ĐV���Ȏ��_����u�֓���k�Ёv�����������A���܂łɗނ̂Ȃ����Ђł��B�M�d�Ȏ������疾�炩�ɂȂ��ЊQ�̎��ԁA���ЁA����lj������I
���k�ЗX�����E��
�����{�X��o�Ŋ�
��2023�N�X���P�����s
���a�T���E�����^96�y�[�W�^�I�[���J���[
���\���E���ʂ͐��쒆�̃C���[�W�ł��B
8415
�؎�r�W���A���A�[�g�E�V���[�Y��T�e�I
�؎�ɕ`���ꂽ������ƃw���ȓ��{�I
���E�e���Ŕ��s���ꂽ�A���{��`���؎�̂��āu�W���|�j�J�؎�v�ƌĂт܂����A���̒��ɂ͎��X������ƃw���ȓ��{��A�u���[����Ȃ�����b�v�Ǝv�킸���Ȃ���c�b�R���ł��܂����{���`����Ă��܂��B
�{���̓W���|�j�J�؎肪�`���A�������남������NIPPON �␢�E�Ɠ��{�̂Ȃ���A���ɗ����ł��Ȃ��\���ȂǁA���E���������{�ς����܂��܂Ȋp�x������グ�Ă��܂��B�����A�I�����s�b�N�A�x�m�R�A�V�����A�A�j��������E�������g�������남������NIPPON�h���ځI�̖{�����A���X�c�b�R�~�����Ȃ��炨�y���݉������B
�y�{���̍\���z
�E��P�� �W���|�j�J�؎�̎O��e�[�}�[������ܗ֤���ې؎�W
�E��Q�� ���{�Ɛ��E�[���j�E�푈�ƕ��a
�E��R�� ���{�̏ے��[�O���l�������j�b�|��
�E��S�� �W���|�j�J�؎薜�؋�
���a�c�i�E��
�����{�X��o�Ŋ�
��2023�N�W���P�����s
���`�T���E�����^112�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͐���r���̌��{�ł��B
�؎�ɕ`���ꂽ������ƃw���ȓ��{�I
���E�e���Ŕ��s���ꂽ�A���{��`���؎�̂��āu�W���|�j�J�؎�v�ƌĂт܂����A���̒��ɂ͎��X������ƃw���ȓ��{��A�u���[����Ȃ�����b�v�Ǝv�킸���Ȃ���c�b�R���ł��܂����{���`����Ă��܂��B
�{���̓W���|�j�J�؎肪�`���A�������남������NIPPON �␢�E�Ɠ��{�̂Ȃ���A���ɗ����ł��Ȃ��\���ȂǁA���E���������{�ς����܂��܂Ȋp�x������グ�Ă��܂��B�����A�I�����s�b�N�A�x�m�R�A�V�����A�A�j��������E�������g�������남������NIPPON�h���ځI�̖{�����A���X�c�b�R�~�����Ȃ��炨�y���݉������B
�y�{���̍\���z
�E��P�� �W���|�j�J�؎�̎O��e�[�}�[������ܗ֤���ې؎�W
�E��Q�� ���{�Ɛ��E�[���j�E�푈�ƕ��a
�E��R�� ���{�̏ے��[�O���l�������j�b�|��
�E��S�� �W���|�j�J�؎薜�؋�
���a�c�i�E��
�����{�X��o�Ŋ�
��2023�N�W���P�����s
���`�T���E�����^112�y�[�W�^�I�[���J���[
���摜�͐���r���̌��{�ł��B
8065
�����Ǝ��W���y����40�b
�j���[�X�^�C���̐؎���W���发�I�Җ]�̑��҂����s�I
�C�y�Ɋy�����ǂ߂āA�E���`�N�������ς��B��D�]�������������u�؎���̒m��Book�v�̑��҂����s����܂����I
���҂͂������A�؎�̔����َ�C�w�|���̓c�ӗ�������B�O���Ƃ͈قȂ�V���Ȑ���A�������̑��ʂȃr�W���A���荞��Ō����A���͓I�Ȑ؎���W�̐��E�B
����A�����Ƃ������u�؎�̒a���v����A�p�P�b�g�A�؎�͂�G�Ɏ���u�؎�̊y���ݕ��v�܂ŁA�؎�a���ȗ��̗��j�Ɠ����̐��E���߂���A������؎�̗̈�ɊF��������ē����Ă����܂��B�nj�A�����Ǝv����ɈႢ����܂���B�؎���W���Ă���ȂɖL���Ȃ��̂ȂƁI
���c�ӗ����E��
���؎�̔����ي�
��2023�N�T��25�����s
��B5�ό`���E�����^88�y�[�W
�i�摜�͐���r���̌��{�ł��B�j
�j���[�X�^�C���̐؎���W���发�I�Җ]�̑��҂����s�I
�C�y�Ɋy�����ǂ߂āA�E���`�N�������ς��B��D�]�������������u�؎���̒m��Book�v�̑��҂����s����܂����I
���҂͂������A�؎�̔����َ�C�w�|���̓c�ӗ�������B�O���Ƃ͈قȂ�V���Ȑ���A�������̑��ʂȃr�W���A���荞��Ō����A���͓I�Ȑ؎���W�̐��E�B
����A�����Ƃ������u�؎�̒a���v����A�p�P�b�g�A�؎�͂�G�Ɏ���u�؎�̊y���ݕ��v�܂ŁA�؎�a���ȗ��̗��j�Ɠ����̐��E���߂���A������؎�̗̈�ɊF��������ē����Ă����܂��B�nj�A�����Ǝv����ɈႢ����܂���B�؎���W���Ă���ȂɖL���Ȃ��̂ȂƁI
���c�ӗ����E��
���؎�̔����ي�
��2023�N�T��25�����s
��B5�ό`���E�����^88�y�[�W
�i�摜�͐���r���̌��{�ł��B�j
8683
�I�[���J���[��厏�̑�12�e
�����O�X��Ƃ̗D�ꂽ�������ʂ��I�[���J���[���^������厏�̑�12�e�A�S�T�e���^�B
�E���u�����t���̊O�M�g�p�̍ŏ����g�p��v
�E�g�c�h�u�v���C�Z����ԃV���[�Y�v
�E�c���T�i�u�������S�K�؎�̔ŕʁ|80�ʔł�100�ʔŁ|�v
�E�e�n�b���u��P�����a�؎�A�A�[�J�C�u�Ƒ����\��v
�E�L�،��u�t�B���s���E�~���_�i�I�Q�����؎�v
���g�c�h�E��
���X�^���y�f�B�A��
��2022�N12��30�����s
��A4���E�����^150�y�[�W�^�I�[���J���[
�����O�X��Ƃ̗D�ꂽ�������ʂ��I�[���J���[���^������厏�̑�12�e�A�S�T�e���^�B
�E���u�����t���̊O�M�g�p�̍ŏ����g�p��v
�E�g�c�h�u�v���C�Z����ԃV���[�Y�v
�E�c���T�i�u�������S�K�؎�̔ŕʁ|80�ʔł�100�ʔŁ|�v
�E�e�n�b���u��P�����a�؎�A�A�[�J�C�u�Ƒ����\��v
�E�L�،��u�t�B���s���E�~���_�i�I�Q�����؎�v
���g�c�h�E��
���X�^���y�f�B�A��
��2022�N12��30�����s
��A4���E�����^150�y�[�W�^�I�[���J���[
8687
�����؎���߂��镨��
1948�N�`72�N�A�ČR�{�����ɒu���ꂽ����B���̒n�ɐ��������p�Ƃ��`�����F�N�₩�Ȑ؎肪�A�������ꂽ�ꏊ�l�X�́u���t�v���^��ł����\�\�B�ČR�ɂ���́A�������{�����A������ݓ����A�����ĕ��A�^�����o�ĕԊҍ��ӂցB�����̎���A�����E����̕����Ǝ��R�𐢊E�ɓ`�����A259��̗����؎���߂��镨��B
���^�ߌ��b�E��
���������_�V�Њ�
��2022�N12��10�����s
���l�Z���^�㐻�E255�y�[�W
1948�N�`72�N�A�ČR�{�����ɒu���ꂽ����B���̒n�ɐ��������p�Ƃ��`�����F�N�₩�Ȑ؎肪�A�������ꂽ�ꏊ�l�X�́u���t�v���^��ł����\�\�B�ČR�ɂ���́A�������{�����A������ݓ����A�����ĕ��A�^�����o�ĕԊҍ��ӂցB�����̎���A�����E����̕����Ǝ��R�𐢊E�ɓ`�����A259��̗����؎���߂��镨��B
���^�ߌ��b�E��
���������_�V�Њ�
��2022�N12��10�����s
���l�Z���^�㐻�E255�y�[�W
8688
�ِF�̒n�}�ǖ{
�卂�n�����@�ɂ��A�ِF�̒n�}�ǖ{�B�����O�̐؎�W�ō��]�����钘�҂��A�L�x�ȃR���N�V��������A�n�}���`���ꂽ�������؎�}�Ă��Љ�A�n�}�̖��́A�n�}��ǂ݉����y���݂��킩��₷���`����B
�����C���v�E��
�����ɂ����[��
��2023�N2��28�����s
���`�T���^�����E199�y�[�W
�卂�n�����@�ɂ��A�ِF�̒n�}�ǖ{�B�����O�̐؎�W�ō��]�����钘�҂��A�L�x�ȃR���N�V��������A�n�}���`���ꂽ�������؎�}�Ă��Љ�A�n�}�̖��́A�n�}��ǂ݉����y���݂��킩��₷���`����B
�����C���v�E��
�����ɂ����[��
��2023�N2��28�����s
���`�T���^�����E199�y�[�W